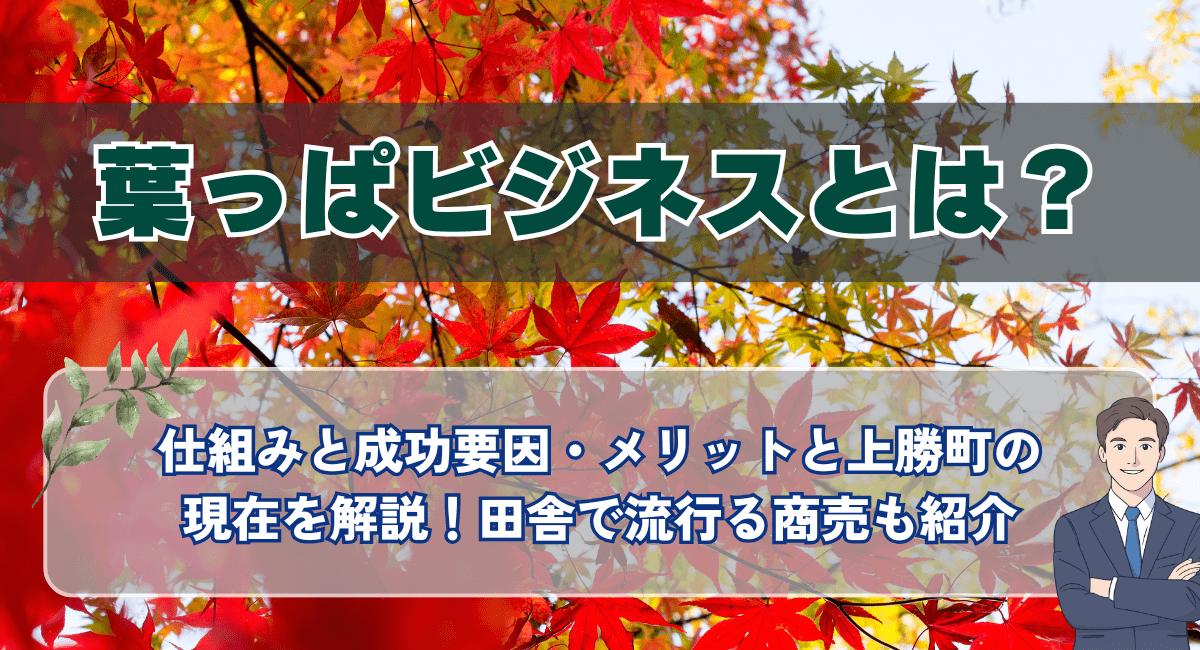
「葉っぱビジネス」という言葉を聞いたことがありますか?
葉っぱビジネスは、徳島県上勝町で生まれ、町の基幹産業へと成長しました。地域の活性化に繋がった成功した県は成功事例として注目を集めていますが、具体的にどのような仕組みのビジネスなのでしょうか。
この記事では、葉っぱビジネスの概要、種類や仕組み、課題や成功事例を紹介します。
目次
葉っぱビジネスとは
葉っぱビジネスとは、季節の葉っぱや花、山菜などを栽培・出荷・販売する農業ビジネスのことを指します。
葉っぱビジネスのうちの約8割が料理の飾りに使われる「つまもの」です。つまものはかつてから存在しましたが、それをメインに扱ってきた農家は存在せず、それぞれの飲食店が独自に入手するのが当たり前でした。この需要に注目して生まれたのが、葉っぱビジネスです。
近年、高齢者や女性が活躍するビジネスとして、注目を集めています。
葉っぱビジネスは1986年頃から徳島県上勝町で始まった
葉っぱビジネスは、徳島県上勝町で始まりました。当時、町の産業は林業や温州みかんの生産によって支えられていました。しかし、1981年に異常寒波が町を襲い、みかんの大部分が出荷不可能になってしまったのです。
そのような町の産業の危機に遭ったことで、当時町の農協職員だった横石知二氏は、地域でできる新しいビジネスについて考えました。そして、「つまもの」の需要と地域資源に注目し、1986年に葉っぱビジネスを行う会社「いろどり」をスタートさせました。
葉っぱビジネスの現在
上勝町で始まった葉っぱビジネスは、地域の資源を活かし町の経済を潤した事例として注目を集めました。現在で、国内の他の地域でも葉っぱビジネスをスタートさせた事例が見られます。
では、葉っぱビジネスはどのような仕組みとなっているのかを次で見ていきましょう。
葉っぱビジネスの仕組み

葉っぱビジネスは、飲食店や葉っぱや花を必要とする、顧客の需要を確認するところから始まります。その後、確認した需要に応じて農家が生産販売を行います。必要となる葉っぱは顧客によって異なります。そのため、農家は多種多様な葉っぱを取り扱わなければなりません。
上の図は、「株式会社いろどり」が実施する葉っぱビジネスの仕組みの例です。JAが受注や生産を担当し、農家が栽培・出荷・販売を実施、そして株式会社いろどりが市場分析や営業を行っています。作業を分担することで、それぞれの強みを最大限に生かすことができ、地域全体の産業発展につながっています。
ICTの活用が成功理由
上勝町の葉っぱビジネスが成功した理由のひとつに「ICT(情報通信技術)」の導入が挙げられます。上勝町では、パソコンやタブレット端末を導入し、農家が専用HPで受注情報や市場情報をリアルタイムで確認できるようにしました。高齢者がパソコンやタブレットを駆使しビジネスを行う姿はテレビでも報道され、注目を集めたのです。
ICTの導入により、各生産者が市場情報や今後の予測を確認できることで、自ら生産量の調整といった計画を立てられるようになりました。また、POSシステムで上勝町の生産者の売り上げ順位を見れるようにしたことで、モチベーションを程よく上げることに成功しました。
葉っぱビジネスの種類
葉っぱビジネスの種類には大きく分けて、つまもの・縁起物・わさび菜の3種類が挙げられます。
つまもの
料理に添えられるつまものは、綺麗な形や色が重要視されます。そのため、美しい形の「南天(ナンテン)」や、青もみじが販売されます。
縁起物
縁起物の葉っぱは、イベントの時期に販売されることが多く見られます。「ゆずり葉」や「ナンテンの樹」が例として挙げられます。
わさび菜
葉っぱビジネスの3つ目の種類が「わさび菜」です。葉わさび・ミニ葉わさび・マイクロ葉わさびと異なるサイズがあります。生産者はサイズごとに販売を行っています。
葉っぱビジネスが注目されている理由
高齢者がICTを活用し行う葉っぱビジネスは、テレビで報道されたり2012年には映画化されたりと、話題を呼びました。ですが、葉っぱビジネスが注目を集めた理由は、ICTの活用だけではありません。
地域資源を上手に活用した事例
上勝町は、今まで「ただの葉っぱ」と見過ごされてきた地域資源を活用したことで、地域経済を活性化させることに成功しました。自分達のすぐ近くにある環境や、物の価値にはなかなか気づきにくいものです。しかし、その需要に気づいたことで、原価ゼロ円のビジネスを生み出すことができました。
そのため、特に過疎化が懸念される地方で活かせるビジネスモデルとして注目を集めています。
女性や高齢者が取り組みやすい
葉っぱビジネスの大きな特徴のひとつに、商品が軽量で取り扱いやすい点が挙げられます。出荷関係のビジネスとなると、重い荷物を運ぶ作業が含まれてしまうことも多々あります。対して、葉っぱビジネスの場合は商品が軽量のため、女性や高齢者でも運営ができると注目されています。
高齢者が活躍し続けられる葉っぱビジネスは、高齢化が進む現代ビジネスのモデルケースとも言えるでしょう。
続いては、葉っぱビジネスのメリット・デメリットを見ていきます。
葉っぱビジネスのメリット
葉っぱビジネスには、大きく2つのメリットがあります。
年収が安定する
年齢に関係なく続けられる葉っぱビジネスは、高齢者の年収の安定につながります。上勝町では年間売上が約1,000万円の高齢者もいるほどです。
日本の高齢者の多くは年金で生活をしています。しかし、年金で生活するのは苦しく、生活保護受給者が増える要因ともなります。+αの収入が生まれることで、生活が楽になり地域に活気が生まれます。
地域福祉の発展につながる
高齢者でも続けられるビジネスの活性化は、地域福祉の発展にもつながります。上勝町では、定年を迎え仕事がなくなった高齢者がやりがいを持って栽培・出荷・販売を行うことで、外に出る機会が増え、健康維持や寝たきり予防ができるようになりました。
また、葉っぱビジネスではタブレットの使用や、パッケージに入れる細かい作業が求められるので、脳の活性化も期待できます。
葉っぱビジネスのデメリットや課題
葉っぱビジネスには、デメリットや課題も存在します。新型コロナウイルスの感染拡大も葉っぱビジネスに大きく影響しました。
コロナ禍による売上減少
葉っぱビジネスは、会席料理店や居酒屋といった顧客をターゲットにしています。そのため、コロナ渦で外食する人が減ったことで、需要が減り大きな打撃を受けました。例えば株式会社いろどりの年商は平常時は約2億円でしたが、コロナ渦で2020年には1億5,000万円まで落ち込みました。
また、葉っぱビジネスは他の農業と同じく、自然状況に左右されます。現在はコロナ禍は落ち着きを取り戻しつつありますが、葉っぱビジネスが決して100%安定した産業ではないという課題が残ります。
後継者問題
葉っぱビジネスの主な需要はつまものであり、若者にとっては今後ビジネスを成長させる余地が小さいと感じてしまうかもしれません。インターンシップで訪れる若者も増えてはいるものの、地方の人口減少は止まらず、後継者問題は大きな課題です。
葉っぱビジネスだけでなく、若い移住者が定住したいと思う町作りが必要です。
葉っぱビジネスの成功事例
最後に、葉っぱビジネスの取組事例を紹介します。
【株式会社いろどり】葉っぱビジネスの生みの親

既に記事の中で紹介した株式会社いろどりは、葉っぱビジネスの生みの親として、現在も活動を続けています。現在では、300以上の種類の葉っぱを全国に出荷しています。農家向けにタブレットの使い方を解説する機会を設けたり、後継者育成のための農業体験の受け入れを行っています。
【フレッシュファーム奥本】ドクダミの育成と農業体験

「フレッシュファーム奥本」は、ドクダミの葉っぱを販売しています。ドクダミは薬草としても有名で、収穫・販売だけでなく収穫体験も開催しています。地域の特性を活かし、ただ栽培して出荷するだけではない、新たなビジネスモデルを導入した事例です。
葉っぱビジネスの失敗例
葉っぱビジネスは成功例が多く注目されますが、準備不足や販路確保の失敗で継続できないケースもあります。ここでは、実際にあった失敗例とその原因を詳しく解説します。
需要予測の誤りによる在庫過多
葉っぱビジネスでは、季節性や需要量を正確に把握することが重要です。しかし、市場調査や取引先との需要確認を十分に行わず、見込みで大量に栽培すると、出荷先が確保できず在庫を抱えてしまう危険があります。
特につまもの用途の葉は使用時期が限られ、鮮度が命のため、保管期間が短く、廃棄につながるケースが多く見られます。これにより、収益どころか廃棄処分費用や人件費の負担が増し、赤字経営に転落することもあります。
需要予測を誤る原因には、経験不足や過去データの未活用、気候や行事の変動要因を考慮しない計画立案が挙げられます。事前に販路や注文を確保してから生産量を決めることが不可欠です。
販路確保の遅れ
葉っぱビジネスの初心者が陥りやすい失敗の一つが、販路確保の後回しです。生産準備や栽培管理に集中しすぎて、出荷時期までに販売先や取引契約が整っていないと、収穫した葉の行き場がなくなります。
特に鮮度の落ちやすい葉は数日で品質が劣化し、価格が急落するか廃棄せざるを得なくなります。また、急遽販路を探そうとしても、安値買い叩きや輸送条件の不備など不利な条件での取引になりがちです。
この失敗は、営業活動や市場開拓を並行して進めなかったことが主な原因です。安定収益を確保するには、生産計画の段階から取引先との関係構築や販路契約を固めておくことが欠かせません。
品質管理の不徹底
葉っぱビジネスにおいて品質は信頼そのものです。鮮度管理や衛生管理が不十分だと、輸送中や保管中に葉が変色・しおれ・傷みを起こし、取引先からの返品やクレームが発生します。
特に高級料理店やホテル向けのつまものは見た目が重視されるため、わずかな変色や傷でも商品価値が失われます。品質管理の不徹底は、収穫から出荷までの時間が長すぎる、適切な温度・湿度管理がされていない、梱包が不適切といった原因から起こります。
一度信用を失うと継続取引が難しくなり、長期的な売上減少につながります。防止には、適切な収穫タイミングや迅速な出荷体制、保冷設備の活用など、品質を最優先にした管理体制の確立が必須です。
田舎で流行る商売!成功例を紹介
近年、田舎の資源や暮らしを活かした新しいビジネスが注目を集めています。ここでは、今後田舎で流行る商売や、これから人気が高まりそうな分野をピックアップし、成功が見込める事例として紹介します。
地域資源を活かした体験型観光ビジネス
田舎ならではの自然や文化、食を体験できる観光ビジネスは、今後さらに需要が高まると予想されます。農業体験や漁業体験、季節の山菜採りや紅葉狩りなど、都市部では味わえない非日常体験は観光客を惹きつけます。
地域の歴史や伝統工芸、地元食材を使った料理教室などを組み合わせれば、滞在型観光としての魅力もアップします。さらに、SNSでの発信や旅行予約サイトの活用により、国内外から集客が可能です。
体験型観光は地域の一次産業と連携でき、農家や漁師の副収入にもつながるため、地域経済の活性化と雇用創出の両面で効果が期待できます。
オンライン販売と連携した農産物直売モデル
インターネットの普及により、田舎からでも全国へ商品を販売できる環境が整いました。農産物直売モデルにオンライン販売を組み合わせることで、地元市場に頼らず安定した売上を確保できます。
旬の野菜や果物、加工食品を定期便として販売すれば、リピーター獲得にもつながります。また、生産者の顔や畑の様子をSNSや動画で発信することで、商品の付加価値が高まり、都市部の消費者からの信頼を得られます。
小規模農家や個人経営でも参入しやすく、初期費用を抑えられるため、スモールビジネスとしても魅力的です。今後は、ふるさと納税やクラウドファンディングとの連携も有効です。
空き家活用による宿泊・飲食サービス
地方の空き家や古民家を活用した宿泊・飲食サービスは、低コストで始められ、独自性を打ち出せるビジネスです。古民家を改装して民宿やゲストハウスにすれば、都会の旅行者や外国人観光客に人気の「田舎体験」を提供できます。
また、カフェやレストランとして営業し、地元食材を使った料理を提供すれば、地域住民の交流拠点にもなります。補助金や移住促進制度を活用すれば改装費用の負担も軽減可能です。
さらに、体験型観光や農業体験と組み合わせることで滞在価値を高め、リピーターを増やせます。地域の景観保全や空き家問題の解決にも寄与する、今後有望な田舎ビジネスです。
田舎に欲しいサービスとは
田舎では都市部にはない不便さや課題がありますが、その課題を解決するサービスが地域の活性化や雇用創出につながっています。ここでは、すでに各地で導入され、成功している田舎のサービス事例をご紹介します。
移動販売による日用品・食品の提供サービス
スーパーやコンビニまで距離がある地域では、移動販売車による日用品や食品の提供が大きな役割を果たしています。実際、全国各地で大手スーパーや地元商店が展開する移動販売は、高齢者や交通手段のない住民から高い支持を得ています。
販売品は野菜や惣菜、日用品など幅広く、住民同士の交流の場にもなっています。特に買い物弱者対策として行政からの補助を受けるケースも多く、安定した運営が可能です。加えて、定期的な訪問により、安否確認や簡単な見守りも兼ねられる点が評価されています。
高齢者向け宅配・見守り支援サービス
地方では独居高齢者が増加しており、食事や生活必需品の宅配と同時に安否確認を行うサービスが成功しています。弁当宅配業者や地元の飲食店、NPOなどが主体となり、決まった時間に訪問して食事を届けることで、栄養管理と健康維持を支援します。
さらに、配達時の会話や体調の確認が孤独感の軽減につながり、家族や地域からも安心感が得られます。自治体との連携により費用補助を受ける事例もあり、持続可能なサービスとして定着しています。
地域資源を活用したコミュニティカフェ
空き家や廃校、古民家を活用したコミュニティカフェは、田舎で成功している地域活性化の事例です。カフェとして地元食材を使った料理やスイーツを提供するだけでなく、住民が集まり交流できる場所としても機能します。特に高齢者や子育て世代、移住者の交流拠点となり、イベントやワークショップの開催にも活用されます。
観光客向けに地域の歴史や文化を発信する拠点としても人気があり、リピーターの増加や地域経済への波及効果が大きいのが特徴です。補助金やボランティアの協力により、低コストで運営を始められる点も成功要因の一つです。
田舎で始めたビジネスの成功例
田舎の特性を活かしたビジネスの成功事例を3つ紹介します。
古民家を活用した一棟貸し宿泊施設
地域の空き家を再活用し、高単価な宿泊プランを提供するモデルが成功しています。 都会にはない「静寂」や「築100年の趣」を価値に変えることで、高い集客力を発揮します。
維持費を抑えつつ、宿泊客に地元の食材を届けることで地域全体に利益をもたらします。
耕作放棄地での高付加価値ハーブ栽培
手入れが困難になった農地を活用し、飲食店向けに特化したハーブ栽培が注目されています。 通常の野菜より軽量で出荷作業が楽なため、少人数のスタッフでも運営が可能です。
希少性の高い品種に絞ることで、全国のシェフと直接取引を行い、高い利益率を実現します。
廃校を利用した体験型キャンプ場
少子化で閉校になった校舎やグラウンドを、キャンプ場やシェアオフィスへ転換した事例です。 既存の設備を活用するため、初期投資を大幅に抑えて事業を開始できます。
「学校に泊まる」という非日常的な体験がSNSで話題を呼び、若年層の呼び込みに成功しています。
葉っぱビジネスの成功事例
田舎で始められるビジネスの中でも、葉っぱビジネスは地域資源を活かしながら安定収益を生みやすいモデルとして注目されています。ここでは、実際に田舎で始めて成功した葉っぱビジネスの事例をご紹介します。
高級料理店向けの「つまもの」出荷で安定収益を実現
ある地方の農家では、自宅周辺で採れる季節の葉を高級料理店向けに出荷する「つまもの」ビジネスを展開し、安定した収益を実現しました。料亭や割烹などでは料理の見栄えを引き立てる飾り葉の需要が高く、季節ごとの種類や品質が求められます。この農家は鮮度管理や梱包方法を工夫し、年間を通して安定供給できる体制を整備しました。
さらに、取引先と直接契約を結び、中間マージンを削減して利益率を向上。天候や市場価格の変動に左右されにくく、少ない面積でも高収益を確保できるモデルとして成功しています。
観光と連携した季節限定の葉っぱ販売モデル
観光地近くの農家グループが、観光シーズンに合わせた葉っぱ販売を行い、成功しています。春は桜の葉や山菜、秋は紅葉や彩り豊かな落ち葉など、季節感のある商品を観光客向けに提供。直売所や道の駅に特設コーナーを設け、観光客が手軽に購入できる仕組みを整えました。
さらに、葉を使った押し花やハンドクラフト体験もセットで販売し、物販と体験の両面から収益を確保。季節限定販売ながら高い利益率を誇り、地域の観光資源と農業の相乗効果を生み出した事例です。
耕作放棄地を活用した地域共同葉っぱビジネス
高齢化や人口減少で増えた耕作放棄地を活用し、地域住民が共同で葉っぱビジネスを立ち上げた成功例があります。放棄地を整備して季節の葉や花を栽培し、出荷や販売を共同で行うことで作業負担を分散。高齢者や主婦、移住者など多様な人材が参加し、地域コミュニティの結束も強まりました。
収益は参加者に分配される仕組みで、農業未経験者でも参入可能。地元の飲食店や市場と直接取引を行い、安定した販路を確保しました。このモデルは地域課題の解決と収益化を同時に実現した好事例です。
葉っぱビジネスや田舎で始めるビジネスに関するよくある質問
葉っぱビジネスや田舎で始めるスモールビジネスは関心が高まっていますが、始め方や必要な資金、販路確保など疑問も多く寄せられます。ここでは、よくある質問とその答えをまとめます。
田舎でも儲かる商売は?
田舎でも安定的に収益を上げられる商売は、地域資源や立地特性を活かしたビジネスが中心です。例えば、地元で採れる農産物や加工品を直売する農産物直売所、農業体験や自然体験ツアーなどの観光体験型ビジネス、そして地元特産品を全国へ届けるオンライン販売などが挙げられます。
また、田舎ならではの空き家や古民家を活用したカフェや宿泊施設も人気です。インターネットやSNSを活用すれば、立地条件の不利を克服でき、都市圏の顧客にもアプローチ可能です。初期投資を抑え、地域の魅力を発信することで、高い収益性と持続性を両立できます。
田舎でできるおすすめの自営業は?
田舎で始めやすい自営業は、地域の自然・文化資源を活かせる分野が強みです。農業や畜産業はもちろん、野菜や果物の加工食品販売、地域の食材を使った飲食店、古民家を改装した民泊などが人気です。
また、竹細工や陶芸などのクラフト制作、地域の風景や動植物をテーマにした写真販売やガイド業も注目されています。インターネット販売や予約サイトを活用すれば、地元外からの集客も可能です。特に田舎は土地や施設のコストが安く、固定費を抑えられるため、小規模から始めて徐々に拡大するスモールビジネスにも向いています。
葉っぱビジネスを始めるのに必要な初期費用は?
葉っぱビジネスの初期費用は規模や設備によって変わりますが、一般的には数万円〜数十万円程度が目安です。主な費用項目として、苗や種の購入費、畑やハウスの整備費、収穫用のハサミや手袋などの道具、出荷用の箱や包装資材があります。
また、品質を保つための保冷庫や輸送用の保冷箱などの設備を導入する場合は、さらに費用がかかります。販路を広げるために、直販サイトや販促用チラシの制作費が発生することもあります。規模を小さく始めれば初期投資は抑えられますが、安定的な品質管理のためには必要最低限の設備投資が重要です。
葉っぱビジネスの販路はどう確保する?
葉っぱビジネスの販路確保には、複数のチャネルを組み合わせることが有効です。代表的な方法としては、地元の飲食店やホテルへの直接販売、農協や市場を経由した卸売、道の駅や直売所での販売があります。
最近では、自社のオンラインショップやECモール(Amazon、楽天など)を活用し、全国の顧客へ販売する事例も増えています。また、SNSでの情報発信により、料理人や飲食店から直接問い合わせを受けることもあります。
安定的な取引を実現するためには、事前に取引先と納期・数量・品質条件を明確にし、信頼関係を築くことが重要です。
葉っぱビジネスで失敗しないためのポイントは?
葉っぱビジネスで失敗を防ぐためには、まず需要調査と販路確保を事前に行うことが不可欠です。市場のニーズや季節ごとの需要変動を把握し、確実に販売できる量だけを生産することで、在庫過多や廃棄を防げます。
また、鮮度や見た目が重視されるため、品質管理体制を徹底する必要があります。収穫から出荷までの時間短縮、適切な温度・湿度管理、丁寧な梱包などが信頼獲得につながります。
さらに、天候不順や需要変動に備え、複数の販路や商品ラインナップを持つことでリスクを分散できます。継続的な改善と顧客対応が長期的な成功の鍵です。
葉っぱビジネスや田舎で始めるビジネスとSDGsの関係性
葉っぱビジネスや田舎で始めるビジネスは、SDGs(持続可能な開発目標)の複数の目標と密接に関係しています。
まず、目標8「働きがいも経済成長も」との関連です。葉っぱビジネスは小規模でも始められ、特に高齢者や子育て世代など、都市部では働きにくい人たちの雇用機会を生みます。農閑期や短時間勤務でも収入につながるため、地域経済の底上げにも寄与します。
次に、目標12「つくる責任 つかう責任」です。葉っぱビジネスは地元で採れる季節の葉や花、山菜を活用するため、輸送による環境負荷が小さく、食品廃棄も最小限に抑えられます。また、自然素材を利用することでプラスチック代替にもつながります。
さらに、目標15「陸の豊かさも守ろう」にも貢献します。放置竹林や耕作放棄地を活用すれば、生態系の保全や景観維持に役立ちます。農業を通して自然との共生を図ることで、持続可能な地域づくりが可能になります。
つまり、葉っぱビジネスや田舎発の小規模ビジネスは、環境・経済・社会の三側面でSDGsの達成に寄与するモデルになり得ます。
まとめ
既に地域に存在した葉っぱを販売するという斬新なアイディアは、葉っぱビジネスという新たなビジネスモデルを生み出しました。
ICTと地域の資源、そして地元の高齢者の知恵とスキルを活かした産業の成功事例です。今後ビジネスを開拓していきたい事業者にとって、参考になる点が多いのではないでしょうか。
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!







