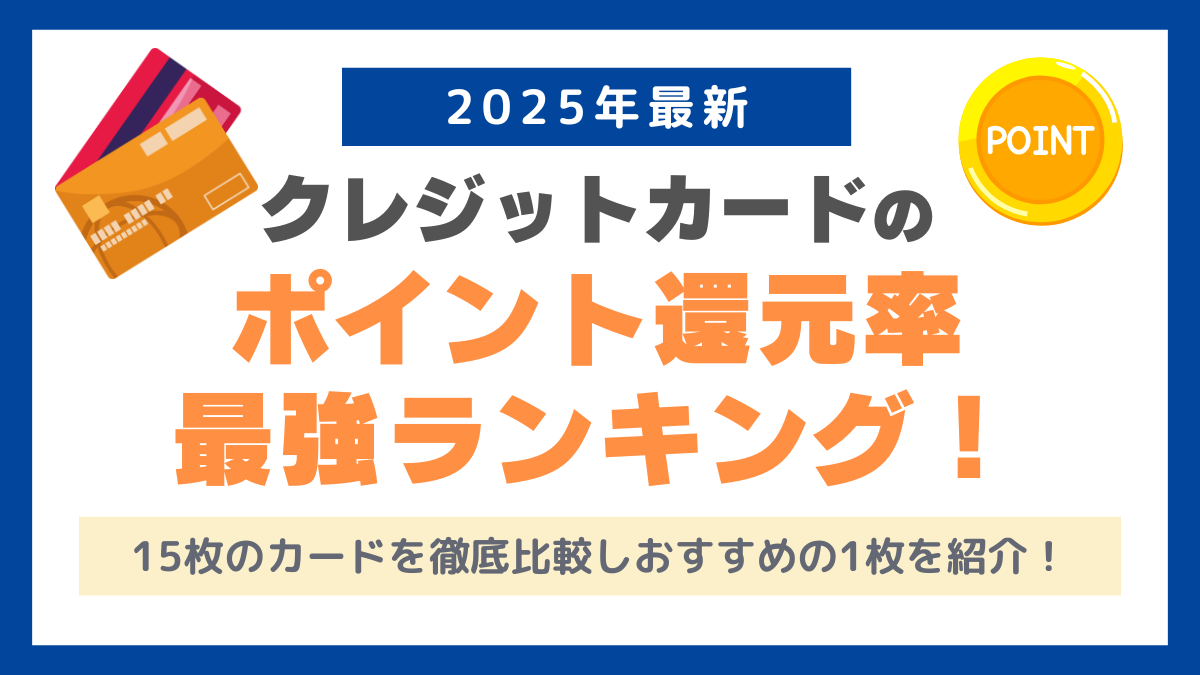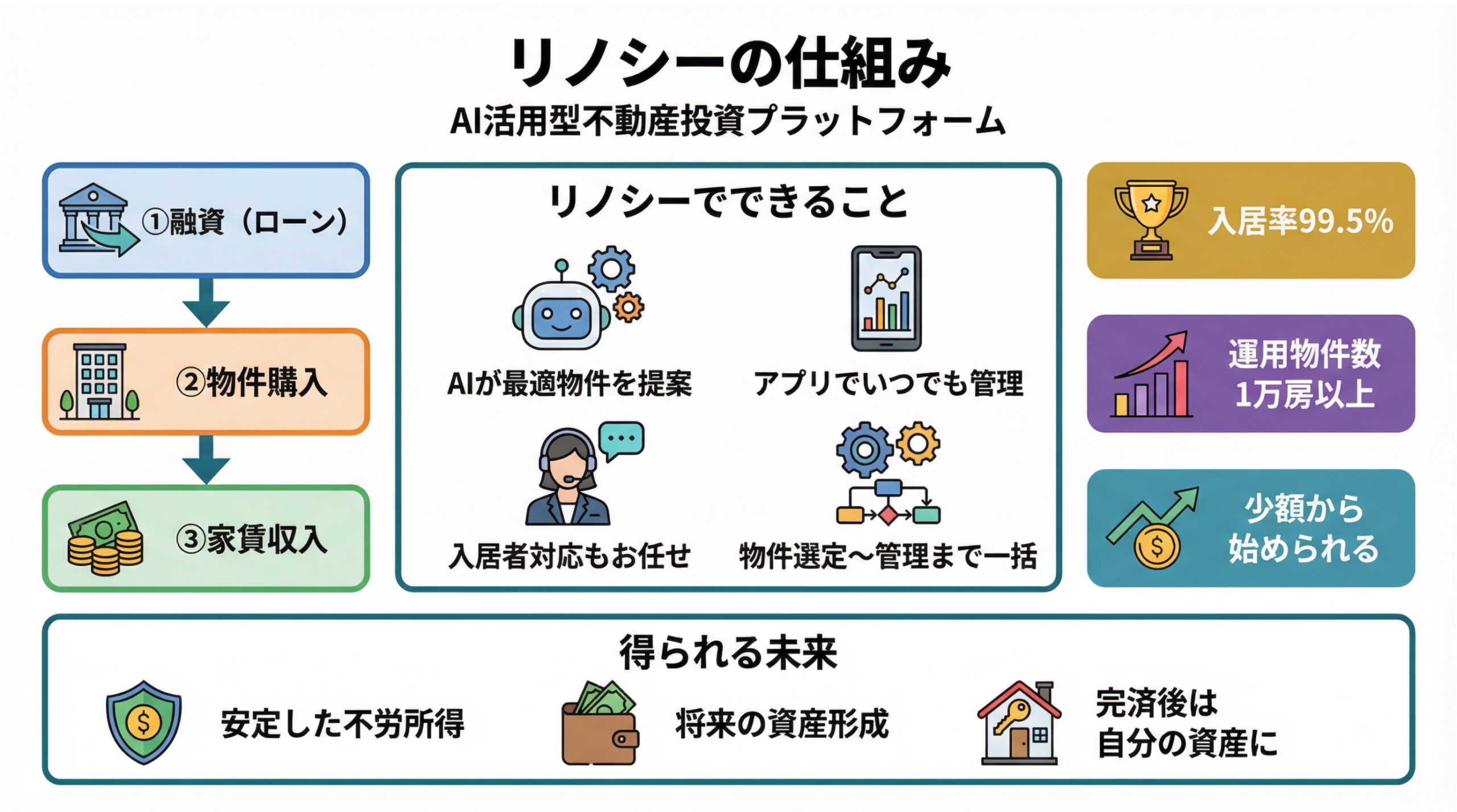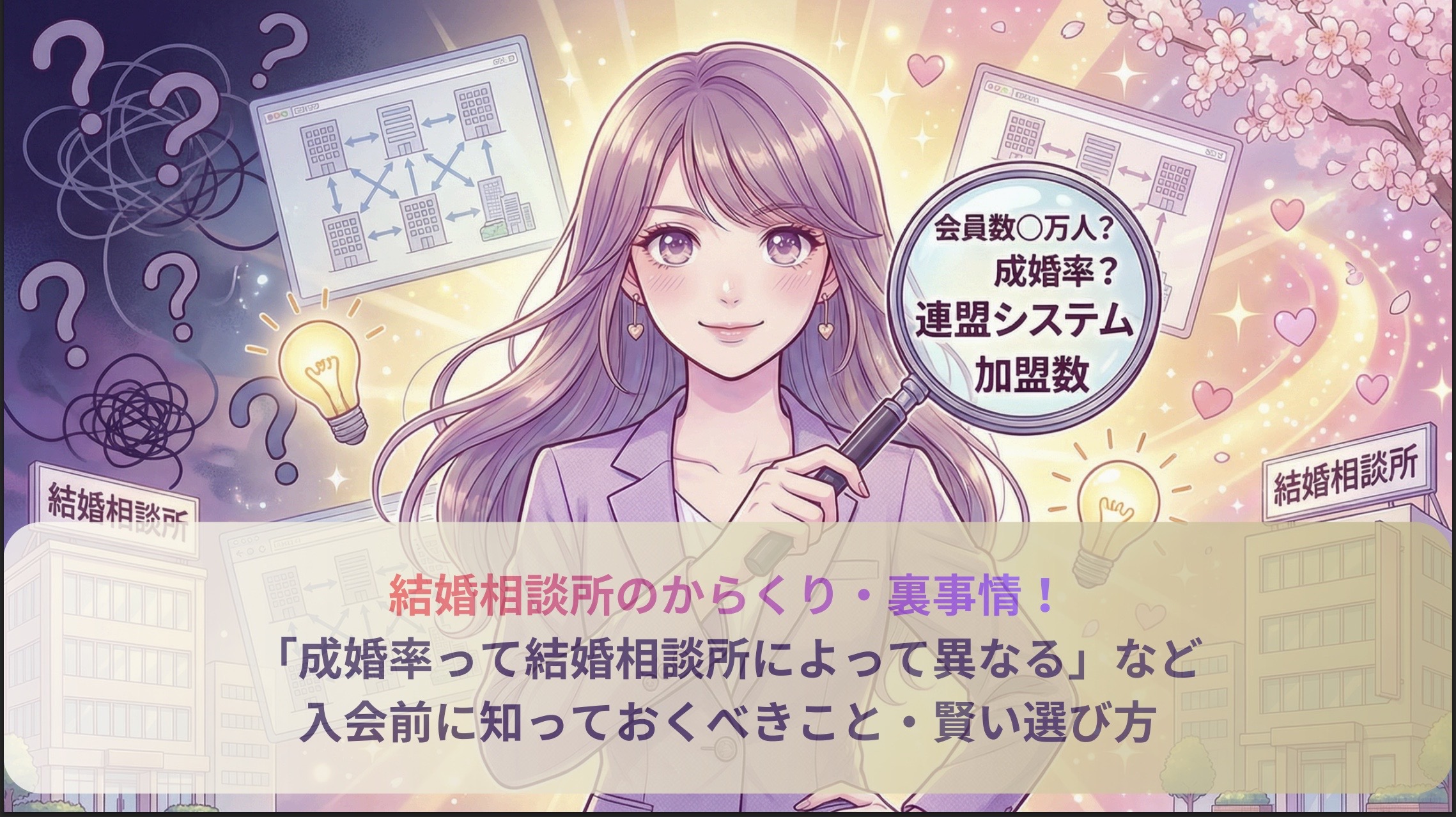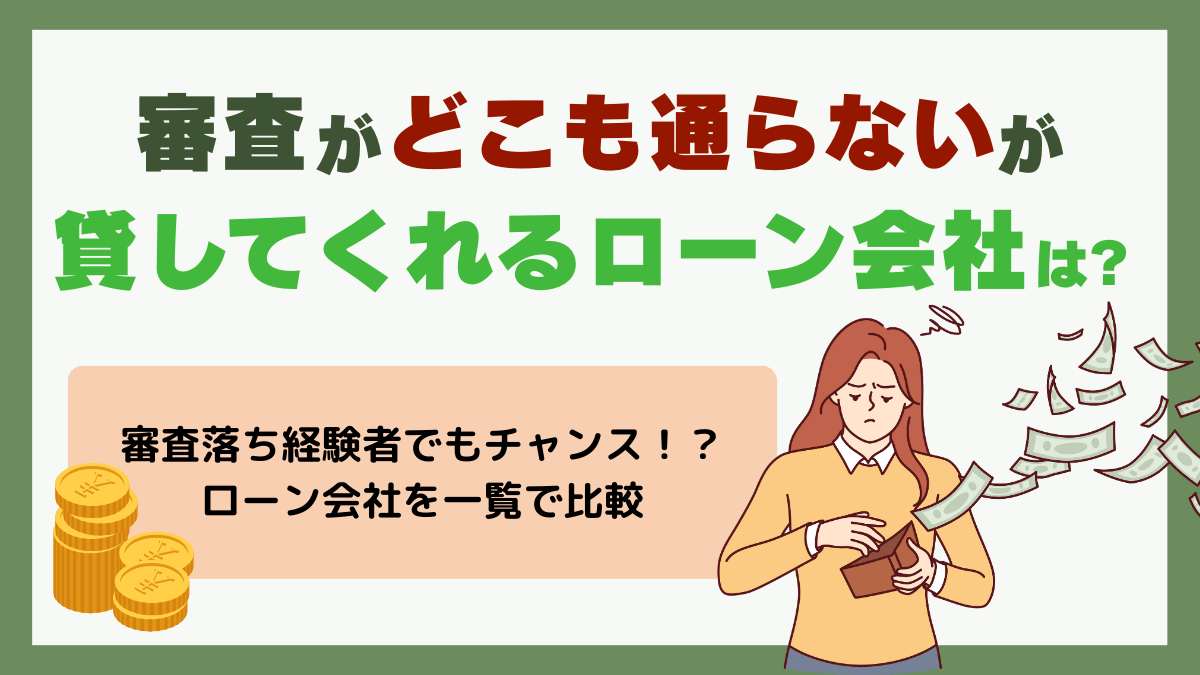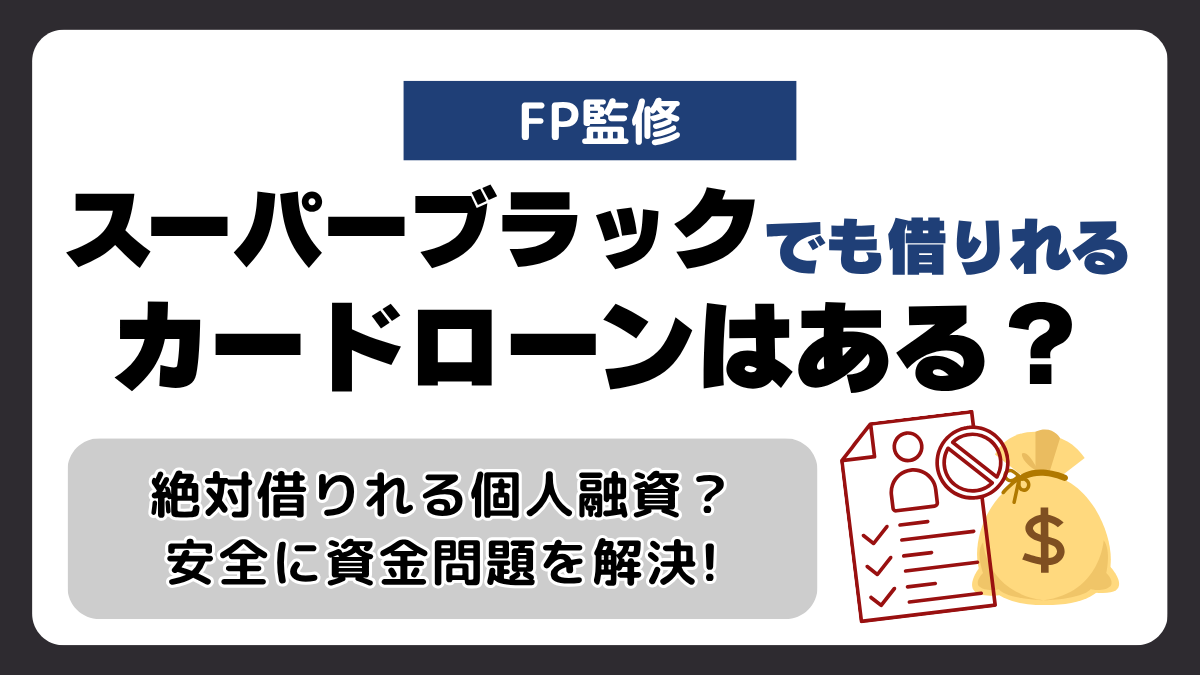500万人。これは2021年の1年間に世界で命を落とした子どもの数で、その半数が1ヶ月以内の乳児です。
この問題を解決するために大切なワードが”乳児死亡率”です。これはどこの国でどのくらい子どもが亡くなっているかを表す数値ですが、日本に住んでいる私たちにとっては、あまり身近な言葉ではないかもしれません。
そこで今回は乳児死亡率とは何なのか、新生児・5歳未満児死亡率との違い、SDGsとの関係も踏まえて解説します。
目次
乳児死亡率とは
乳児死亡率とは「生まれてから満1歳になる日までに死亡する確率」です。以下の計算式で導き出され、出生数1,000人あたりの死亡数で表記されます。
(c)年間乳児死亡数×1,000
(a)乳児死亡率=――――――――――――
(b)年間出生数
厚生労働省がまとめている人口動態総覧を参考に、日本を例にして計算してみましょう。
- (b)に入るのが、2018年の年間出生数918,400人
- (c)に入るのが年間乳児死亡数1,748人
つまり、(a)乳児死亡率は1,000人あたり1.9人となります。乳児死亡率は各国ごとに数値がまとめられており、その国の衛生状況や医療情勢などを把握するのに役立ちます。
乳児死亡率と混同しやすい死亡率に「新生児死亡率」「5歳未満児死亡率」があります。この2つは生まれてからの期間に違いがあるため、次で確認しましょう。
新生児死亡率との違い
新生児死亡率とは「生まれてから生後28日以内に死亡する確率」のこと。
つまり、生まれたての赤ちゃんの健康状態に焦点を当てています。乳児死亡率と同じく、表記は出生数1,000人あたりの死亡数を指します。
5歳未満児死亡率との違い
5歳未満児死亡率とは「生まれてから5歳未満に死亡する確率」です。上記2つの死亡率と同じように、1,000人あたりの死亡数を表します。
この2つの指標はどちらも貧困、衛生問題について考える際には大切なものなので、覚えておくと良いかもしれません。
乳児死亡率の計算方法
乳児死亡率とは、生後1年未満で死亡した乳児の数を、同じ年に出生した子どもの総数で割り、1,000人あたりで表した数値です。一般的には次のような計算式で求められます。
乳児死亡率(‰)=(乳児死亡数 ÷ 出生数)× 1,000
たとえば、ある年に1,000人の子どもが生まれ、そのうち5人が1歳未満で亡くなった場合、乳児死亡率は「(5 ÷ 1,000)×1,000=5.0‰」となります。
この指標は、国や地域の医療体制、衛生環境、栄養状態、母子保健サービスなどの水準を示す重要なバロメーターです。乳児死亡率が高い国では、妊産婦の栄養不足や医療へのアクセス困難、感染症対策の遅れなどが原因となっていることが多く、単なる統計ではなく、その国の生活環境の現れともいえます。
日本のように乳児死亡率が極めて低い国では、新生児医療や予防接種、母子支援制度の充実が背景にあります。計算方法を理解することで、数値の意味や他国との比較もより正確に把握できるようになります。
【世界の現状】データでわかる乳児死亡率が高い国最新ランキング
| 順位 | 国名 | 乳児死亡率 (‰) |
|---|---|---|
| 1 | アフガニスタン | 101.3 |
| 2 | ソマリア | 83.6 |
| 3 | 中央アフリカ共和国 | 80.5 |
| 4 | 赤道ギニア | 77.4 |
| 5 | シエラレオネ | 71.2 |
| 6 | ニジェール | 64.3 |
| 7 | チャド | 62.5 |
| 8 | 南スーダン | 60.1 |
| 9 | モザンビーク | 58.2 |
| 10 | マリ | 57.4 |
参考:ワールドファクトブック
乳児死亡率の定義や、新生児・5歳未満児死亡率との違いがわかったところで、次は世界の現状をデータから見ていきます。
日本の乳児死亡率の推移
日本の乳児死亡率は、戦後から現在にかけて大幅に改善されてきました。1950年には1,000出生あたり60人以上の乳児が亡くなる状況でしたが、医療技術や衛生環境の発展により、年々低下しています。
1980年代には既に1桁台となり、2022年の厚生労働省の統計では1,000出生あたり1.7人という世界でもトップクラスの低水準を記録しました。
この推移は、日本の母子保健制度や乳幼児健診、予防接種体制、NICU(新生児集中治療室)の充実などが背景にあります。また妊婦健診の普及により、ハイリスク出産の早期対応が可能となっていることも、乳児死亡率の低下に寄与しています。
今後もさらなる低下が期待される一方で、出生数自体が減少しているため、少数の事例でも統計的に影響が大きく出る点には注意が必要です。
とりわけ乳児死亡率が高い国
| 国 | 1990年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) | 2018年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) |
|---|---|---|
| 中央アフリカ共和国 | 117 | 84 |
| シエラレオネ | 156 | 78 |
| ソマリア | 108 | 77 |
| ナイジェリア | 125 | 76 |
| チャド | 112 | 71 |
日本ユニセフ協会によると、乳児死亡率が高いのはサハラ以南のアフリカ、西部・中部アフリカ地域です。
特に、中央アフリカ共和国・シエラレオネ・ナイジェリアなどといった国の乳児死亡率が高くなっています。ヨーロッパやアジアの国と比較しながら確認してみましょう。まずは、2018年の乳児死亡率が高い国を5つ抜粋しました。
1位は中央アフリカ共和国で、乳児死亡率は1,000人あたり84人。1990年の乳児死亡率と比べてみると低下している傾向にありますが、いまだに多くの乳児が犠牲になっています。
上記で挙げた5つすべてがサハラ以南のアフリカ地域の国です。下記の地図を見ても、乳児死亡率が高い国が密接していることがわかります。
ヨーロッパの乳児死亡率
| 国 | 1990年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) | 2018年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) |
|---|---|---|
| フィンランド | 6 | 1 |
| フランス | 7 | 3 |
| オランダ | 7 | 3 |
| ベルギー | 8 | 3 |
| チェコ | 10 | 3 |
ここでは5つの国をピックアップしました。なかでもフィンランドは、1,000人あたり1人と死亡率を抑えられています。その他の国々も全体的に死亡率が低いことがわかります。
次にアジアの国も見てみましょう。
アジアの乳児死亡率
| 国 | 1990年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) | 2018年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) |
|---|---|---|
| 日本 | 5 | 2 |
| 韓国 | 13 | 3 |
| 中国 | 42 | 7 |
| モンゴル | 77 | 14 |
アジアは地域によって数値が大きく異なるため、ここでは東アジアと南アジアにわけて乳児死亡率を見ていきましょう。まずは東アジアの乳児死亡率をご覧ください。
1990年と2018年の乳児死亡率を比べると減少傾向にあります。中国とモンゴルに関しては1990年からかなり減少しているのがわかりますね。
次に南アジアのデータをご覧ください。南アジアはサハラ以南のアフリカ地域と同じく貧困が多い地域となっています。そのため、まだまだ乳児死亡率が高くなっているのが現状です。
| 国 | 1990年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) | 2018年の乳児死亡率(出生数1,000人あたりの死亡数) |
|---|---|---|
| タイ | 30 | 8 |
| ベトナム | 37 | 16 |
| インド | 89 | 30 |
| ミャンマー | 82 | 37 |
1990年の乳児死亡率に比べるとインドやミャンマーは低下していますが、1,000人あたり30人が死亡しているため、改善する必要があるでしょう。
このようにどの国も1990年から比較すると状況が改善されつつあることがわかります。とはいえ数値が高い国はまだまだ多いのが現状です。
乳児死亡率の高い国が偏っている理由
では、なぜ乳児死亡率が高い国は偏った地域に集中しているのでしょうか。
乳児死亡率が高い理由として
- 医師不足
- 栄養失調
- 出産後の定期健診がない
などが挙げられます。それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
医師が不足している
私たちは、
「具合が悪いなら病院で診てもらったら?」
「妊娠したかもしれないから産婦人科に行ってみようかな」
などといった会話を当たり前のように交わしますよね。しかしそれは、十分に医者や病院があるから成り立っているもの。
日本は、人口約400人に対し医者が約1人いる計算ですが、乳児死亡率が高い国では、数万人に1人医者がいるかどうかという現状です。※1
ただでさえ乳児は免疫がなく病気のリスクが高いのに、万が一病気になっても治療が受けられず、そのまま亡くなってしまうケースが多く発生しています。
妊娠・出産時の母親の健康状態が良くない
そもそも妊娠・出産時の母親の体調が良くない可能性があります。
サハラ以南のアフリカ地域においては、貧困問題が解決していません。さらには干ばつや洪水などの自然災害により、貧困が加速してしまっている状況です。
貧困地域で暮らしている妊婦は、安全な水はもちろん十分な食事をとることができません。そのため胎児にも栄養が行き渡らず、生まれたあとも体が弱く、栄養失調で亡くなってしまう事態が起きています。※2
出産前後の定期健診が受ける割合が低い
乳児死亡率の高い国では、出産前後の定期健診を受けている女性の割合が少ない傾向にあります。
2017年の日本ユニセフ協会のデータによると、サハラ以南のアフリカでは46%しか定期健診を受けられていない結果が出ています。※3
健診を受けていなければ、乳児の健康状態や妊婦・胎児の病気の早期発見ができません。
また、産後に健診を受けられないと授乳や育児の相談ができないため、何かあった際に母親が対応できないケースもあるでしょう。乳児死亡率を下げるためは、出産前後の定期検診がいかに大切なのかがわかります。
このように、乳児死亡率が高い地域では、共通する課題を抱えているのです。これらの問題は、日本の数値と比較すると、より深刻さを実感できます。
日本の乳児死亡率が低い理由
日本ユニセフ協会が出している2019年のデータによると、2018年の日本の乳児死亡数は1,000人あたり1人となっています。
1990年以降、日本の乳児死亡数は減少しており、他国と比べてもかなり少ない数で抑えられています。日本の乳児死亡率が低い理由として、1960年~1970年の高度経済成長期以降、
- 公衆衛生の改善
- 医学の発達
- 日本発祥である母子手帳の普及
などの対策が挙げられるでしょう。※4
このように国によって大きく数値が異なる「生の不平等」はあってはならないもので、早急に改善しなければならない課題と言えるでしょう。
乳児死亡率を減らすための解決策
具体的な解決策として、
- 字が読み書きできない人のための識字教育
- インフラの整備と衛生教育の普及予防接種の普及
- 予防接種
- 女性への教育
の4つが挙げられます。1つずつ見ていきましょう。
字が読み書きできない人のための識字教育
まず解決策として挙げられるのは「識字教育」です。
読み書きができないと、次のような困難に陥る可能性があります。
- 危険な場所に行ったとしても文字が読めず回避できない
- 薬を手に入れても注意書きが読めない
- 仕事の選択肢がない
私たちは文字が読めるからこそ、危険を事前に察知できたり、説明書きを読んで物を購入できたりします。その一方で乳児死亡率が高い国では、教育を受けられないことで文字の読み書きができない人が多数います。
例えば中央アフリカ共和国やチャドなどは、成人の識字率が40%未満というデータが出ています。つまり国の半分以上の国民は、自国の言葉の読み書きができないのです。
識字教育が整えれば、どのような薬が必要なのか、妊産婦が気をつけなければならないことなどが書かれた本が読めるようになることも考えられ、乳児死亡率も下げられる可能性があります。
インフラの整備と衛生教育の普及
次に挙げる解決策は「インフラ整備と衛生教育の普及」です。
5歳未満の乳幼児が亡くなる原因は主に、
- 肺炎
- 下痢
- マラリア
の3つと言われています。
それらは安全な水の確保や手洗いの習慣を身に付けることで防げる病気です。しかし乳児死亡率が高い国では、
- 手を洗いたくても水道がない
- 石鹸も普及していない
- トイレがない
など、そもそもインフラが整っていません。乳児死亡率を下げるためには、家のすぐ近くに安全な水がある、清潔なトイレを設置するなどの対策が必要です。
そしてインフラを整備すると同時に、手を洗うことの重要性などの衛生教育を普及させることも大切でしょう。
予防接種
感染症やあらゆる病気の免疫をつけるために必要な予防接種。しかし乳児死亡率が高い地域では、予防接種の普及が進んでいない現状があります。その原因としては、
- 教育を受けられないことで予防接種の重要性がわからない
- ワクチンを打つ技術を持つ医療従事者が不足している
などが挙げられます。
ユニセフの活動などによって接種の数は増加しているものの、大幅に数値を改善するには、さらに多くの協力が必要となるでしょう。
女性への教育
女性への教育も乳児死亡率を下げるために必要な対策です。識字教育はもちろんのこと、
- 薬の正しい飲み方
- 予防接種の重要性
- 妊娠時の体のケア
など、さまざまな知識を伝えることが求められています。とはいえ私たちが想像している以上に、サハラ以南のアフリカなどの途上国では男女間の格差は開いています。
途上国で学校に行けるのは男性がほとんどで、女性は家の仕事をまかされ、自分の意思と反して結婚を強いられたり、治療を受けさせてもらえなかったりするケースが多く見られるのが現状です。
女性への教育を普及させるためにも、ジェンダー格差を是正する取り組みを同時に展開していく必要があるでしょう。
日本の乳児死亡率が低い理由
日本の乳児死亡率は、世界でも最も低い水準にあります。2023年の統計では、乳児死亡率は1,000出生あたり1.8人と報告されており、OECD諸国の中でもトップクラスです。この極めて低い数値には、いくつかの重要な要因が影響しています。
まず、母子保健制度の充実が大きな要因です。日本では、妊娠・出産に関する公的支援が手厚く、母子健康手帳の配布や定期的な健診制度により、妊婦や乳児の健康状態を早期に把握できます。また、出生直後から乳児健診や予防接種スケジュールが整備されており、感染症や先天的疾患への対応も迅速に行われます。
次に、医療技術と新生児医療の高度化も見逃せません。NICU(新生児集中治療室)を備えた医療施設の整備が進み、早産や低出生体重児に対する医療ケアの水準が非常に高くなっています。特に都市部では、24時間対応可能な周産期センターの体制が整っており、緊急時の対応力が高いです。
さらに、妊婦への保健指導や生活習慣の啓発も、間接的に乳児死亡率の低下に寄与しています。妊娠中の喫煙・飲酒のリスクについて広く啓発されており、出産前から健康的な生活を心がける女性が増えています。
これらの制度的・技術的背景が相まって、日本は安定して世界最低水準の乳児死亡率を維持しています。
乳児死亡率を下げるための企業の取り組み
ここまで乳児死亡率について詳しく見てきました。これらの問題は、国や支援団体の取り組みだけでは解決まで多くの時間を要してしまいます。そこで大切なのが企業の取り組みです。
ここでは、乳児死亡の減少に向けた取り組みを実施している企業を紹介します。
サンド株式会社
サンド株式会社は、ジェネリック医薬品やバイオシミラー(バイオ後続品)などを取り扱っている製薬会社です。SDGsの目標3の達成に向けて、高品質な医薬品や医療サービスを支援しています。
サンド株式会社は2015年「新しい命&新しい希望(New Life&New Hope)」というプロジェクトをエチオピアで立ち上げました。プロジェクト内容は以下の通りです。
途上国の医師は、十分な医療訓練を受けられていません。
そのため、患者にどのような治療を行うべきか判断できる医師や助産師が少ないという問題があります。現地の助産師が適切な処置が行えるようになれば、乳児死亡率を下げることにつながります。
高品質な医薬品はコストがかかり、途上国に行き渡らないという状況にあります。
加えて、途上国には大きな病院が少なく、緊急を要する場合でも治療を受けるために2時間かけて病院に行かねばなりません。高品質な医薬品が常に手に入るようになれば、乳児だけでなく妊婦や病気になった人々の命も救える確率が上がります。
現在も、薬を必要としている人々が20億人以上いると言われており、サンド株式会社は10億人の患者に医薬品を届けるという目標を掲げています。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャーム株式会社は、紙おむつや衛生用品などを中心に、赤ちゃんの健康と発展途上国の生活環境向上に貢献する企業です。SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」に向け、衛生教育支援を通じて乳児死亡率の低下に取り組んでいます。
ユニ・チャームは、2011年からアジアやアフリカ諸国で「母子の健康支援プログラム」を展開。プロジェクト内容は以下の通りです。
多くの途上国では、妊産婦や乳児の感染症予防に必要な知識や設備が不足しています。ユニ・チャームは、衛生的な紙おむつの提供だけでなく、現地の助産師や母親に向けて、衛生管理・清潔な育児環境づくりの研修を行っています。これにより乳児の感染症リスクを低下させ、乳児死亡率の改善に寄与しています。
対象地域の赤ちゃんと家族には、紙おむつや育児衛生用品を無償で提供。衛生面の向上に加えて、育児負担の軽減や心のゆとりにもつながっています。また、各家庭の衛生習慣を改善するため、ポスターやパンフレットを配布し、住民の意識改革にも取り組んでいます。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
株式会社 明治
株式会社明治は、乳幼児向け粉ミルクや栄養食品の開発・販売を通じて、世界の子どもたちの健やかな成長を支援している企業です。
SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標2「飢餓をゼロに」に貢献すべく、発展途上国の栄養改善に取り組んでいます。
明治は2010年代からアジア・アフリカ地域において、栄養支援プログラムを展開しています。代表的な取り組みは以下の通りです。
栄養不足が深刻な国・地域では、乳幼児の発育不良や死亡率の上昇が問題となっています。明治は、母乳の代替品となる高品質な粉ミルクや、栄養補助食品を現地NGOや保健機関と連携して提供。特に生後6か月以降の離乳期に必要な栄養素を補えるよう設計されています。
物資の提供に加えて、現地の保健師・母親に向けて、栄養・衛生・育児方法に関するセミナーや冊子の配布を行っています。正しい調乳方法やミルクの保存、衛生環境の整え方などを指導することで、乳児の病気や栄養失調のリスクを減らす取り組みです。
これらの活動により、現地での乳児死亡率の低下や母親の知識向上に貢献しています。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
乳児死亡率の削減のために私たちにできること
乳児死亡率は問題の規模が大きいため国や団体、企業が取り組むべき課題のように見えます。しかし、私たちにも解決に向けてできることはあるのです。
ここでは個人でできる3つの方法を紹介します。
乳児死亡率が高い国の状況を知る
まず、乳児死亡率が高い国の状況を知るというアクションがとても重要です。
状況を知っていれば「寄付をする」「現地の人の話を聞いてみる」など、自分なりにどのような行動をすれば良いか考えられるようになり、今まで見てきた景色が変わってくるでしょう。
現代では、さまざまな方法で状況を知ることができるようになりました。たとえば
- NPO法人のサイトを見てみる
- 乳児死亡率が高い国について書かれた書籍や映画を観る
などといった方法があります。乳児死亡率が低い日本で生活している私たちにとっては、かなり衝撃的な事実を知らされることになるでしょう。
下記に途上国の状況を知ることができるサイト、書籍を載せておいたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
寄付をする
乳児の死亡率が高い国について知ることができたら、寄付をするのも個人でできることの1つです。寄付をすることでワクチンの普及につながります。
たとえば「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」では、毎月募金「子どもワクチンサポーター」に参加することが可能です。毎月3,000円を寄付すると、1,800人の子どもたちにワクチンを届けることができます。
NPO法人やユニセフのサイトを見ると、詳しいプロジェクト内容や寄付できるものなど確認できるので、ぜひチェックしてみてください。
発信してみる
いろいろな媒体から情報を集めたら、周りの人たちに発信してみましょう。「しっかり説明しないと」「情報をまとめて発信しないと」など考える必要はありません。実情を知って、自分が思ったことを自分の言葉で伝えるのがとても大切です。
多くの人が知ることで、寄付などの輪が広がったり、もしかすると新しいアイディアが生まれるかもしれません。
友人との何気ない会話で「実はこういう本or映画を読んだんだ」と発信してみるだけでも大きな一歩。得た知識を自分だけで留めるのではなく、周りに発してみましょう。
「乳児死亡率」は17ある目標のうち、特にSDGs3「すべての人に健康と福祉を」と関係しています。
目標3では「母子保健を増進し、主要な感染症の流行に終止符を打ち、非感染性疾患と環境要因による疾患を減らすことを含めて、あらゆる年齢のすべての人々の健康と福祉を確保する」という目標が掲げられています。
なかでも乳児死亡率と関係しているのは、目標3のターゲット2です。
すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。
ターゲットでは直接、乳児死亡率については触れていません。しかし、生まれてから28日以内の新生児や、5歳未満児の予防可能な死亡を根絶するのは、1歳未満に亡くなる乳児を減らすことが重要になるのです。
乳児死亡率に関するよくある質問
ここでは、乳児死亡率に関するよくある質問に回答します。
乳児死亡率が高い国に共通する特徴は?
乳児死亡率が高い国には、いくつか共通する要因があります。まず最も大きな影響を与えるのが「医療インフラの不足」です。適切な医療施設が整っていない、あるいは医療従事者が少ない地域では、出産時や乳児期に必要な処置が遅れ、死亡リスクが高まります。
また、栄養不良や予防接種の普及率が低いことも、感染症による乳児死亡の要因になります。さらに、政治的不安や紛争、自然災害の頻発といった社会的不安定さも、妊産婦や乳児にとって大きなリスクとなります。
教育水準が低く、衛生環境が整っていない地域では、母親が適切な育児知識を得られないことも影響しています。
乳児死亡率が低いと出生率も高くなる?
一般的に、乳児死亡率が低い国ほど出生率が低い傾向があります。これは逆説的ですが、医療が発達し子どもが健康に育つことが見込まれる社会では、親が「たくさん産まなくても良い」と判断するためです。
一方、乳児死亡率が高い国では「何人かは亡くなるかもしれない」という前提で多くの子を持つ傾向があり、結果的に出生率が高くなることがあります。
ただし、これは単純な因果関係ではなく、経済発展や女性の教育水準、避妊手段へのアクセスなど複数の要素が絡んでいます。乳児死亡率と出生率の関係は、医療や教育、経済などの社会基盤の発展度合いを示す1つの指標でもあります。
先進国でも乳児死亡率が高いケースはある?
先進国であっても、すべての地域が低い乳児死亡率を保っているわけではありません。たとえばアメリカでは、国全体としての医療水準は高いものの、人種間・地域間の格差により一部の州や貧困層では乳児死亡率が高い傾向があります。
特にアフリカ系アメリカ人の乳児死亡率は、白人の2倍近いというデータもあります。このように、先進国でも社会的格差や医療へのアクセス不平等が解消されていないと、高い死亡率を引き起こす可能性があります。
また、難民や移民の流入が多い国では、医療体制が一時的にひっ迫し、統計に影響を与えることもあります。
乳児死亡率とSDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関係
ここまで乳児死亡率の大まかな概要について確認してきました。実は近年、乳児死亡率の改善に対する関心が高まりつつあります。その背景にはSDGsの存在があるのです。
この章では、乳児死亡率とSDGsの関係について見ていきましょう。
SDGsとは「Sutainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称です。2015年9月の国連サミットで、参加国すべての国が賛同し採択されました。
SDGsでは「地球上に誰一人取り残さない」という誓いとともに、2030年までに解決すべき17の目標と、達成に向けた具体的な行動指針として169のターゲットが掲げられています。
まとめ
乳児死亡率の高い国の現状を中心に、新生児・5歳未満児死亡率の違いや乳児死亡率の削減のために個人ができることについて解説しました。
「いますぐに乳児死亡率を下げなければ!」と考えてしまうと、ハードルが高い印象を受けますよね。しかし1人1人が少しずつ行動すれば状況が変わるかもしれません。
まずは考えるだけでなく、行動してみることが大切です。ぜひ書籍や映画などを見て現状を知ることからはじめてみてくださいね。
参考文献
※1 ユニセフ「SDGs CLUB」
※2 国連開発計画(UNDP)ゴール4 子どもの死亡率を減らそう,国連広報センター「貧困をなくそう」,ワールドビジョン「乳児死亡率が高くなる原因は? 生まれた日に亡くなる子どもは世界で90万人」
※3 ユニセフ「世界子供白書 2017」
※4 ユニセフ「世界子供白書2019」,nippon.com「赤ちゃんが無事に育つ国 : 乳児死亡率は世界最低レベル、母子手帳も貢献」,厚生労働省「我が国における健康をめぐる施策の変遷」
※5 ユニセフ 「2021年の5歳未満児死亡数、500万人 死亡数減少も、多くの国でSDGs達成困難か」
この記事を書いた人
スペースシップアース編集部 ライター
スペースシップアース編集部です!
スペースシップアース編集部です!