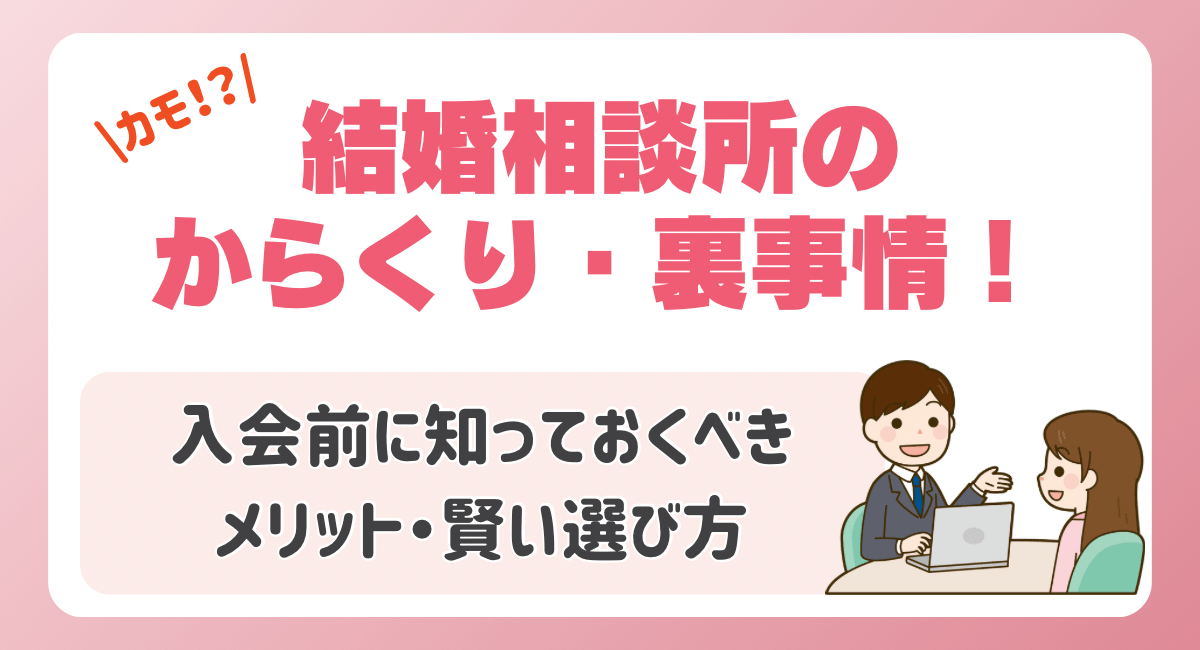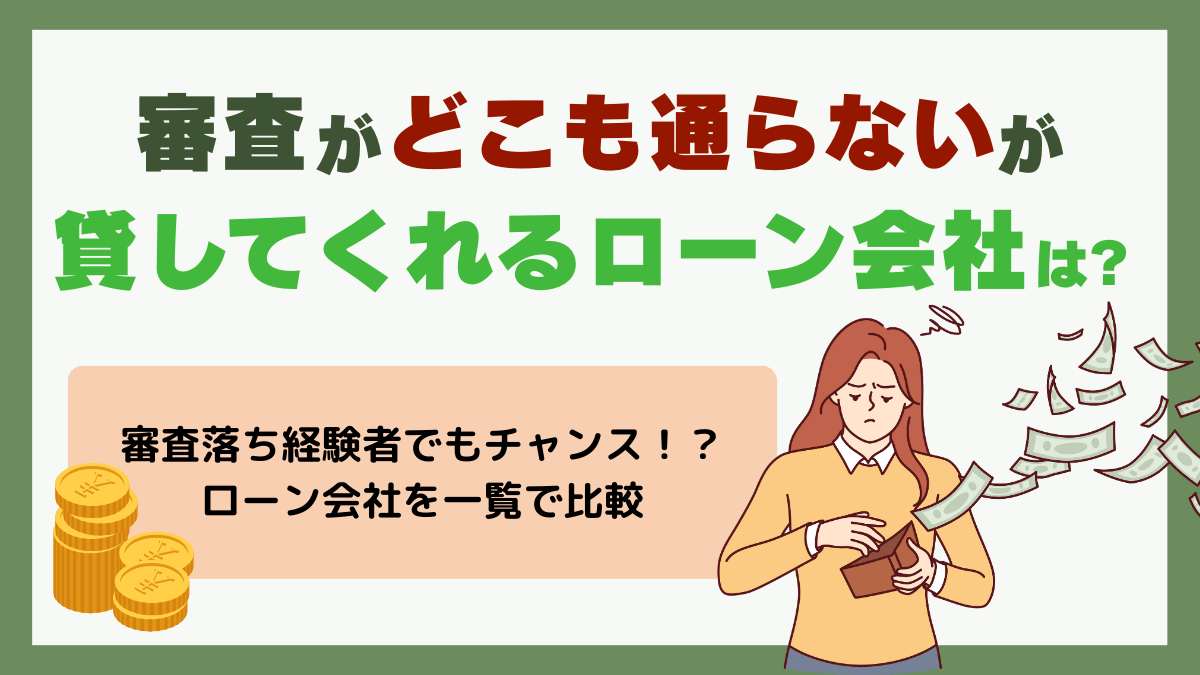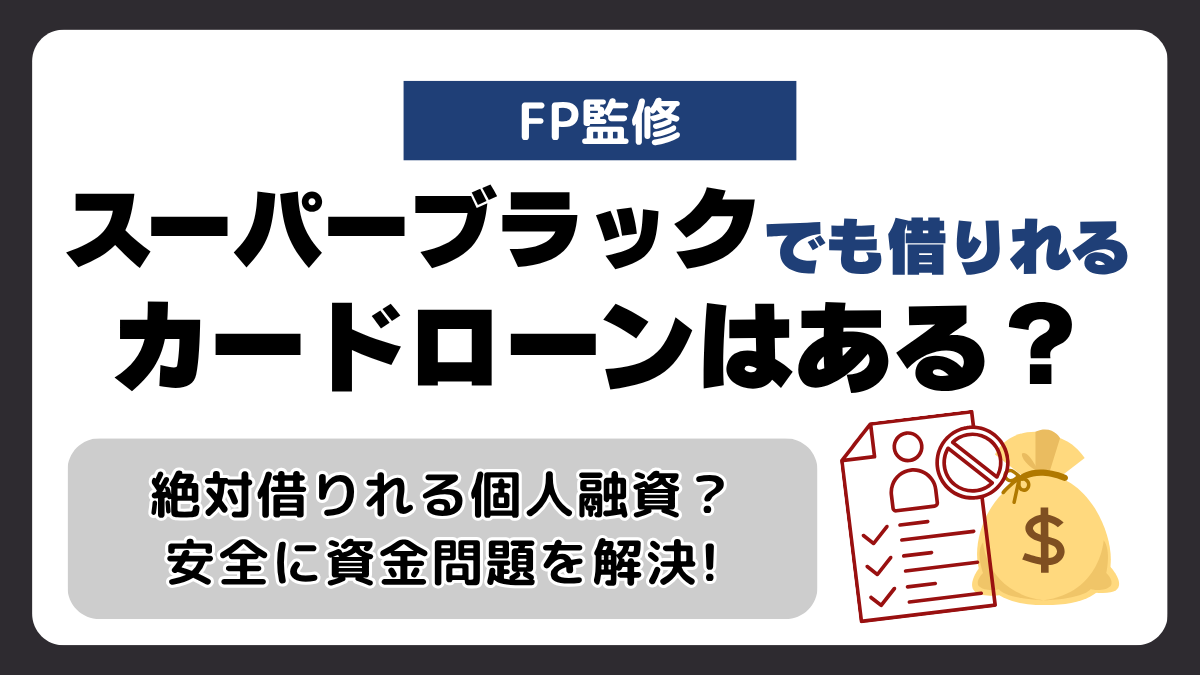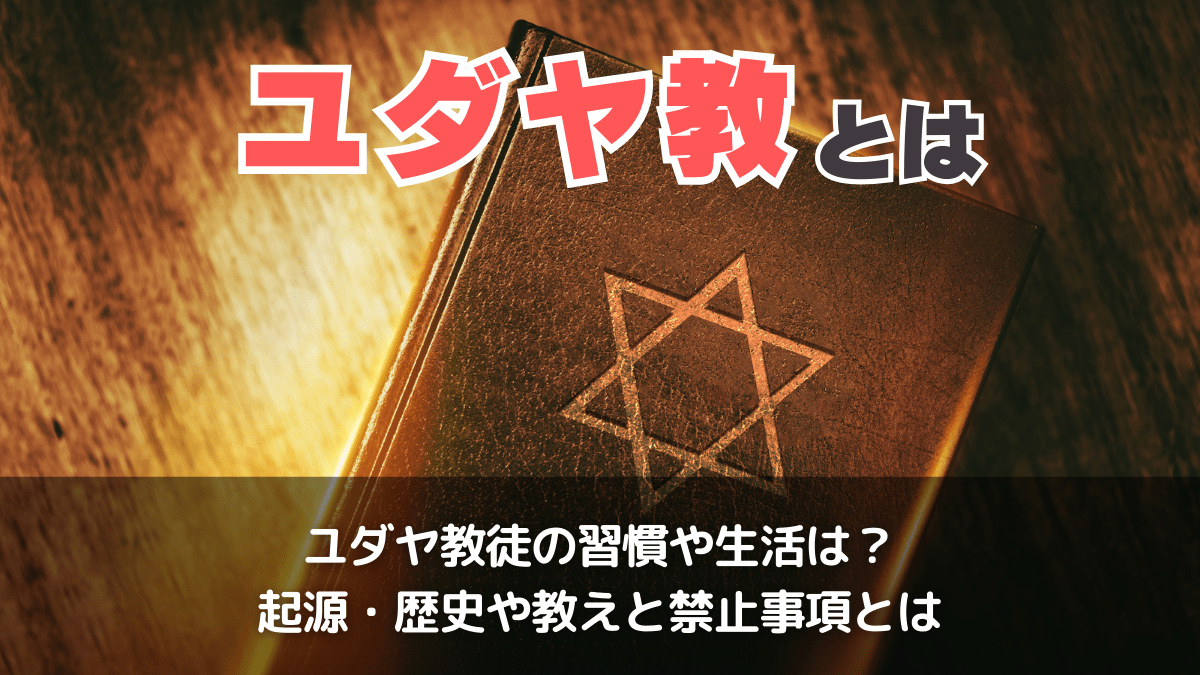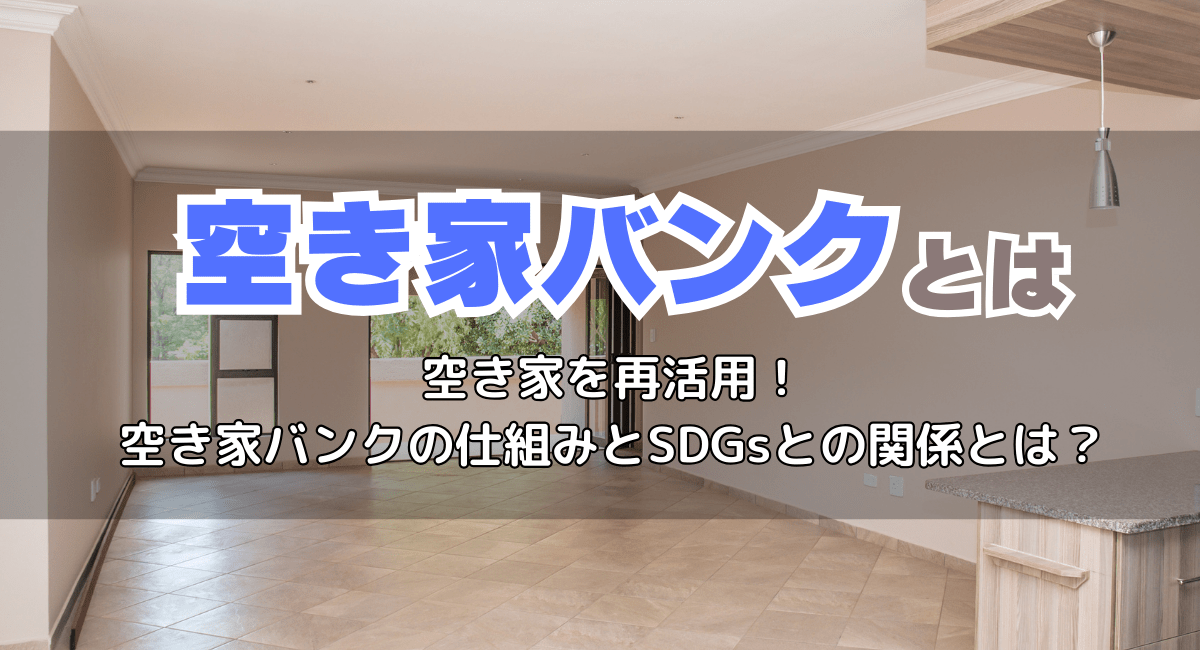
近年、地方を中心に問題となっているのが空き家問題です。これを放置しておくことは、今後の私たちの生活のみならず、環境面にも悪影響をもたらします。
その解決策として注目されているのが空き家バンクです。この記事では、空き家バンクについて詳しく説明していくと同時に、持続可能な暮らしやSDGsとの関連についても紹介します。
目次
空き家バンクとは?制度について簡単に解説
空き家バンクとは、簡単に言えば自治体が地元の空き家情報を集めて、そこに住みたい人を募集し、引き合わせる、という制度です。
空き家バンクの仕組み
具体的には、自分の持っている空き家を売りたい、貸したいと望む所有者からの登録を受け、自治体、主に市や町が公式サイトに空き家バンクのページを作って情報を公開します。
そして物件情報を見た人が住んでみたいと申し出たら、物件の所有者に紹介するものです。ただし自治体では不動産の契約業務は行えないため、委託を受けた宅建業者や不動産会社の仲介で行います。
空き家バンクは自治体に加えて民間が運営するケースも
空き家バンクを運営しているのは、主に自治体です。最近ではこの他に、民間団体やNPOなど行政以外が運営を担うケースや、行政と企業やNPOが連携して運営するケースも増えています。
平成29年からは、国土交通省の選定により(株)LIFULLとアットホーム(株)の2社が「全国版空き家バンク」の運用を始めました。これにより自治体が管理する全国の空き家バンクの物件を一括して見られるため、空き家探しや自治体へのコンタクトもより簡単にできるようになっています。
※必ずしも全ての空き家バンクが登録されているわけではありません。また物件情報は全国版と自治体サイトとの間で相違が生じる場合もあります。物件の検索は全国版と自治体サイトを併用することをおすすめします。
空き家バンクはその地域への定住を狙いとしている
行政が展開する空き家バンクの目的は、不動産業で利益を出すことではありません。その目的のひとつはあくまでも地域への移住・定住であり、地元に住んでくれる人を増やすことです。
最初は都市部からのUターンやIターン希望者の定住促進策の一つとして、主に過疎化に悩む農山漁村地域で行われていましたが、近年は地方の中核都市部でも導入が進んでいます。
空き家バンク制度ができた理由や背景
では、こうした空き家バンク制度は、どのような経緯で作られたのでしょうか。その背景には、空き家を放置することで発生する問題が、自治体に悪影響を及ぼすため、国が対策を定めたことにあるのです!
その対策が「空き家対策特別措置法」という法律です。
空き家対策特別措置法が関係している
この「空き家対策特別措置法」では、主に持ち主が空き家を放置せず、適切に管理するよう定めています。ではなぜ空き家物件の所有者は、誰も住まなくなった家を放置しておくのでしょうか。
現在の法律では、土地に住居、特に1戸につき200㎡以内の家屋が建ってさえいれば、更地に比べて標準額の6分の1という固定資産税の軽減措置がされています。
この住宅用地の特例があるため、住む人がいないにもかかわらず放置されている空き家が出てくるのです!しかし、こうした空き家が増えた結果、
- 老朽化による崩落・倒壊の危険がある
- 廃材や家財道具、ゴミによる衛生状態の悪化
- 不法侵入、不法投棄・害獣の住み付きなど治安の悪化
などの問題がおき、結果的に景観が損なわれ、地域価値の低下をもたらしてしまいます。そのため「空き家対策特別措置法」では、こうした危険な空き家を「特定空き家」と認定し、持ち主に改善を求めることにしました。
一度「特定空き家」に認定されると、上記の住宅用地の優遇がなくなって固定資産税が最大6倍になるばかりか、取り壊しにかかる補助金もなくなることもあります。
そのため自治体は、空き家が特定空き家に認定されないように、持ち主に対して空き家の修繕や利活用を呼びかけます。そしてその受け皿として制度化したのが、空き家バンクです。
少子高齢化と地方の過疎化が進んだため
空き家バンク制度が生まれた大きな理由のひとつが、少子高齢化と地方の過疎化です。若年層の都市部への移住や高齢者の施設入所などにより、地方の住宅が空き家になるケースが急増しました。
特に農村や山間部では、住む人がいなくなった家が放置され、近隣の景観や防災、治安面での課題が深刻化。こうした状況を放置すれば地域の衰退が加速するとして、国や自治体は対策を迫られるようになりました。
空き家バンクは、こうした背景から空き家を新たな住民や事業者に再活用してもらうための制度として整備されたものです。空き家を地域資源と捉え、活用することで移住促進や地域再生につなげようという意図があります。
空き家の放置による社会問題が顕在化したため
空き家の放置が深刻な社会問題として注目されるようになったことも、空き家バンク制度が誕生した大きな背景です。老朽化した空き家は、倒壊や火災のリスクを高めるだけでなく、不法侵入や不法投棄、害獣の住み着きといった治安・衛生上の問題も引き起こします。
また、放置された家が目立つことで、周囲の不動産価値が下がったり、地域の景観が損なわれたりすることもありました。
こうした問題に対処するために、2015年には「空き家対策特別措置法」が施行され、自治体による空き家の指導・管理が制度化されました。空き家バンクは、この流れの中で「放置ではなく利活用へ」という方針に基づいて生まれた仕組みです。
空き家バンクが注目されている理由
空き家バンクは平成27年4月時点において全市町村の約4割、令和元年度で全国の約7割の自治体が既に設置済みであるといわれ、地方自治体が取り組む空き家対策の中でも最も多く使われている方法です。
ではなぜこれだけ多くの自治体が空き家バンクに注目し、導入しているのでしょうか。
年々増加傾向にある空き家の数
まず最も大きな理由は、日本全国で空き家の数が増加していることです。
このグラフは、総務省統計局による平成30年住宅・土地統計調査|住宅及び世帯に関する基本集計の中の空き家数と空き家率の推移を調査した結果です。
ここに見られるように、日本では既に住宅の数に対して世帯数の数が上回っています。つまり「家余り」状態です。日本でこれだけ空き家が増えた原因としては
- 少子高齢化による人口減少
- 都市部への集中による過疎化
- その間も新築住宅は建てられている
ことが挙げられます。さらに空き家は、今後も増加することが見込まれています。
2018年の時点での国内の空き家率は13.6%となっていますが、野村総合研究所の試算によると2033年には、この割合が30.2%に上るとされています。
空き家を積極的に利活用してこの状況を少しでも食い止めるために、空き家バンクに期待が高まっているのです。
移住者による人口増加
空き家を有効に活かすことができるということは、そこに住む人が増えていくということでもあります。
過疎化に悩み地方創生に力を入れている地方自治体にとっては、人口増加のために、移住者が住みやすい物件をより効果的に紹介できることは重要な施策なのです。
地方移住や二拠点生活への需要の増加
【社会増減市町村数の推移(過疎地域以外と過疎地域)】
ストレスの多い都会暮らしを離れ、より豊かで余裕のある生活を求めて地方へ移住をする人々、あるいは移住を検討している人はここ数年増加しています。
【特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センター(東京)問合せ・来場者数の推移】
また、コロナ禍によるテレワークの普及などで、地方移住や二拠点生活への需要が増えていることも見逃せません。
定年を迎える中高年だけではなく、ワークライフバランスを重視した働き方を望む現役世代にとっても、空き家バンクは便利なシステムとして注目されています。
空き家バンクを利用するメリット
空き家バンクには、家を探している人、空き家の処分に困る所有者、自治体にとってもメリットがあります。ここではさらに踏み込んで、その具体的な内容を見ていきましょう。
通常よりも安く空き家を買える・借りられる
空き家バンクは営利目的で運営されていないため、不動産会社による仲介手数料はありません。また、新しく土地を取得して新築で家を建てるよりも格安で家が買えたり、借りたりすることも可能です。
地域活性化につながる
過疎化に悩む自治体にとっては、人口減少に歯止めをかけられるだけでありません。外からの住人を受け入れることで街全体に活気が戻り、それまでとは違った商売や文化事業が立ち上がる契機ともなります。
古民家カフェなどの店舗にも利用できる
自分の思い描くビジネスや文化活動を始めたいと思うなら、空き家バンクは魅力的な選択肢です。登録されている物件は居住用だけではなく、店舗として利用ができるものも多数あります。
資金の問題で都会での起業や開業をあきらめていた方でも、地方に活路を見出せばチャンスは広がります。
空き家バンクには補助金制度もある
空き家バンクを利用することで、自治体から補助金が出され、実質的により安く物件が手に入るケースもあります。
補助金制度を活用して安く買える・借りられる可能性も
実施されている補助金には、以下のようなものがあります。
- 空き家等改修やリフォームへの補助金
- 空き家購入補助金制度
- 家財道具等処分費用への助成金
- フラット35の金利優遇措置
補助金・助成金の内容は自治体によって異なります。移住を検討している自治体のホームページでご確認ください。
空き家バンク登録のメリット
空き家バンクに登録することで、空き家を「使われない資産」から「地域活性化に貢献する資産」へと変えることができます。
所有者にとっても、利用希望者にとってもメリットは多く、自治体が仲介することで安心してやりとりができるのも魅力です。ここでは主なメリットを3つに分けて紹介します。
空き家を有効活用できる
空き家を長期間放置していると、老朽化や倒壊のリスクが高まるほか、固定資産税や修繕費などの維持管理コストが発生し続けます。さらに、雑草の繁茂や不法侵入といったトラブルを招き、近隣住民との関係が悪化することも少なくありません。
こうした悩みを解決する手段の一つが、空き家バンクへの登録です。空き家バンクに登録することで、賃貸や売却といった形で空き家を有効活用でき、所有者自身の負担を軽減できます。
また、空き家が新たな住居や店舗、地域交流の場として活用されることで、地域貢献にもつながります。手放すのではなく「誰かに役立ててもらう」という視点で、資産としての活用価値を高めることができるのが、空き家バンク登録の大きなメリットです。
登録や利用が無料でできる自治体が多い
空き家バンクは、多くの自治体が運営している公的な取り組みであるため、登録料や利用料が無料のケースがほとんどです。通常の不動産売買や賃貸契約では、仲介手数料や広告費が発生しますが、空き家バンクではそれらの費用を抑えながらスムーズにマッチングが行えます。
また、物件によっては「無料で借りられる」ケースや、改修費用の一部を自治体が補助してくれる制度もあり、利用希望者にとっても大きなメリットがあります。
特に地方移住やセカンドライフを検討している人にとっては、初期費用を抑えて理想の住まいを手に入れられるチャンスとなります。自治体によってはサポート体制も整っており、安心して登録・利用できるのも魅力のひとつです。
地域とのつながりが生まれる
空き家バンクを通じた移住や定住は、単なる物件の取得にとどまらず、地域コミュニティとの深いつながりを生むきっかけにもなります。多くの自治体では、利用希望者に対して地域の人々との交流機会を提供しており、移住後も孤立することなく新たな生活をスタートできます。
また、地域行事への参加や、地元住民との日常的なやり取りを通じて、自然とその土地に馴染んでいけるのも空き家バンクならではの魅力です。
地方では高齢化や人口減少が進む中、空き家の活用を通じて地域に若い世代が定着することは、まちづくりの観点でも歓迎されています。地域に溶け込みながら暮らしたいと考える人にとって、空き家バンクは非常に有効な手段といえるでしょう。
空き家バンクのデメリット
一方で、空き家バンクにもデメリットがないわけではありません。
新築住宅や空室物件とは異なり、空き家の状況や持ち主の事情は多種多様なため、思わぬ問題が発生することもあります。また、自治体の裁量や権限ではできないこともある、ということを理解する必要もあります。
仲介役がいないため自身で交渉しなければならない
繰り返しになりますが、基本的に自治体は不動産の仲介業務を行うことができません。所有者との交渉は利用者自身が行うことになるため、ほとんどの自治体では地元の宅建業者や不動産業者に空き家バンクの仲介を委託しています。
当然、利用者自身でこうした業者との相談や話し合いを行わなければならず、慣れていない人にはややハードルが高いと感じるかもしれません。
物件情報の詳細を現地まで確認に行くことも
空き家バンクでは、物件に関する情報が詳しく載っていない場合があります。
- 畑はどのくらいか
- トイレは洋式か和式か
- 敷地はどこまでの範囲なのか
- 壁や床の傷みはどの程度なの
かなど、実際に見なければわからない点もでてきます。
もちろん通常の賃貸物件でも事情は変わりませんが、空き家の状態は持ち主のそれまでの生活が反映されているため、通常以上に気を配らなければなりません。
貸し手と借り手のミスマッチに注意
空き家バンクに関わるデメリットで多いのが、貸し手である所有者と借り手との認識の違いです。主なものとして、
- 家具・家財道具の撤去はどうするのか
- リフォームや改修はできるのか
- 現状維持を望むのか
- 賃貸の場合いつまで貸せるか
などです。
また、「応相談」物件の場合、両者の想定金額で折り合いがつかないこともあります。こうしたミスマッチを回避するために、できれば仲介業者の立会いのもと、早い段階でお互いの合意を得ることが必要です。
空き家バンクの問題点
空き家バンクは自治体が運営する安心感のある仕組みですが、実際に利用する際にはいくつかの注意点や問題点もあります。
制度を正しく理解しないまま登録・利用すると、思わぬトラブルや失敗につながる可能性もあるため、事前にデメリットを把握しておくことが大切です。ここでは代表的な3つの問題点を紹介します。
掲載物件の情報が古い・少ないことがある
空き家バンクの物件情報は、自治体が一つひとつ手作業で管理していることが多いため、民間の不動産ポータルサイトと比べて情報が少なく、更新頻度も低い傾向があります。
すでに成約済みの物件が掲載されたままになっていたり、詳細な写真や間取り図が不十分だったりすることも珍しくありません。また、そもそも登録されている物件数が少なく、選択肢が限られてしまう地域も多く存在します。
希望する条件に合う物件を見つけるには、定期的に自治体のサイトを確認したり、直接問い合わせるなどの手間がかかる点に注意が必要です。
物件の状態が悪くリフォームが前提の場合も
空き家バンクに掲載されている物件の中には、数年間放置されていたものや、老朽化が進んでいるものも多く含まれています。そのため、契約後にリフォームや大規模な修繕が必要となるケースがあり、結果的に予算を大きく超えてしまうこともあります。
とくに「無料」や「格安」とうたわれている物件ほど、建物の状態に問題を抱えていることが多く、安易に飛びつくと後悔する原因になります。
現地での内見や専門家による建物診断を行い、修繕の可否や費用感を事前に確認しておくことが、失敗を避けるポイントです。
契約条件や地域ルールが複雑な場合がある
空き家バンクの物件は、自治体独自の補助金制度や契約ルールが定められていることがあり、それらを十分に理解せずに契約を進めてしまうとトラブルにつながる恐れがあります。
たとえば「移住者のみ利用可能」「定住を前提とする」など、特定の条件を満たさないと契約が無効になるケースや、地域の自治会への参加義務など、生活面でもルールが存在することがあります。
また、契約形態も売買・賃貸・譲渡と多様で、内容が曖昧な場合も。空き家バンクを活用する際は、必ず自治体の担当者としっかりやり取りし、契約条件や地域のルールを明確に把握しておくことが大切です。
空き家バンク制度の利用方法
では実際に、空き家バンクを利用して物件を買いたい、借りたいという移住希望者に向けて、空き家バンクの利用方法を紹介していきます。細かい手順やルールは自治体によって異なりますが、大まかな流れは一緒です。
最初に、自分が移住を希望する自治体のホームページを通して、空き家バンクに利用登録します。空き家バンクへのリンク先がわからない、住みたい市町村が空き家バンクに参加しているかわからない方は、全国版空き家バンクから入るのもいいでしょう。
利用登録はウェブ上で行える所もあれば、募集要項をプリントアウトして郵送やFAXで受け付ける所もあります
気になる物件が見つかったら、空き家バンクの問い合わせフォーム、もしくは電話等で物件について問い合わせます。多くの場合、ここで担当する現地の宅建業者や不動産業者を紹介されます。物件の下見や内覧の予約もここで申し込みます。
実際に現地を訪れ、希望する物件を見学します。ただし、所有者の意向によっては内覧ができないこともありますので事前に確認するようにしましょう。移住促進に熱心な自治体はおためし移住ツアーなどのイベントも企画しているので、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。
空き家の購入または入居を決めたら、物件の所有者と条件を確認し、契約の交渉に入ります。
多くの場合【2】で紹介された宅建業者や、不動産業者の仲介のもとで行われます。お互いに納得できる円満な契約になるように、疑問や不安な点はここで全て洗い出し、所有者の方と確認していきます。
空き家バンクに対する自治体の取り組み事例
空き家バンクの活用は、単に物件を紹介するだけでなく、地域課題の解決や移住促進にもつながる取り組みです。
全国の自治体では、地域の特色やニーズに応じた独自の支援策を導入しており、空き家の再生や定住支援が進んでいます。ここでは、具体的な3つの自治体の事例をご紹介します。
長野県伊那市|空き家バンク+移住体験住宅の提供
長野県伊那市では、空き家バンク制度と連動して「移住体験住宅」の貸し出しを行っています。これは、空き家を利用する前に一定期間地域での暮らしを体験できる仕組みで、移住後のミスマッチを防ぐ効果があります。
さらに、伊那市は空き家改修のための補助金や、Uターン・Iターン希望者への就職支援制度も用意しており、移住希望者にとって非常に手厚い環境です。
自治体の担当者が個別に相談に乗る体制も整っており、空き家活用だけでなく、地域との橋渡しまでを支援する丁寧な取り組みが評価されています。
岡山県真庭市|「空き家見守り隊」で放置リスクを回避
岡山県真庭市では、空き家の登録前に問題が発生しないよう「空き家見守り隊」を設置しています。このチームは地元住民やNPOなどと連携し、定期的に空き家の現地確認や簡易清掃、倒壊のリスク確認を行います。
空き家バンクに登録される前段階から自治体が積極的に関与することで、物件の状態を良好に保ち、利用希望者との信頼構築につなげています。
また、空き家バンク登録後も、リフォーム補助金制度や移住者向けの就農・創業支援制度などを組み合わせ、空き家の「放置→活用」の流れを丁寧に支えています。
大分県豊後高田市|空き家バンク専用サイトと相談窓口を設置
大分県豊後高田市は、空き家バンクの専用ウェブサイトを立ち上げ、物件情報の検索性や透明性を高める取り組みを行っています。写真や間取り、周辺環境まで詳しく掲載されており、遠方の移住希望者でも安心して物件を検討できる設計です。
また、市役所内には空き家相談専門の窓口を設け、税制・リフォーム・補助金など幅広い分野の相談に対応しています。
さらに、空き家を活用してカフェやゲストハウスを開業した事例もあり、住むだけでなく地域活性化の拠点としても注目されています。市全体で空き家利活用を後押しする体制が整っています。
空き家バンクの活用事例
ここでは全国各地の自治体から、空き家バンクの利用により物件の成約が増えた例をご紹介します。
移住や田舎暮らしに興味がある、地方で物件を探したいとお考えの方にとっては、成功している空き家バンクがどんな取り組みをしているのか知ることはとても心強いものになるでしょう。
(これらの自治体では、現時点で登録物件がないところもあります。詳細は各自治体の公式サイトなどでご確認ください。)
【充実の移住サポート&オンライン内覧】秋田県由利本荘市
秋田県南部に位置する由利本荘市は、豊かな自然と農産物、住環境の良さから、住みたい田舎として人気の高い自治体です。
由利本荘市の空き家バンクは、物件の登録要件を緩和するなど運用を見直し、県外在住者向けにオンライン内覧を行うなどの工夫で、昨年度の2倍の登録・成約数につなげています。
市の「移住まるごとサポート課」では、移住希望者に特化した職業や住まいの紹介の他、子育て、医療・介護や地域情報に至るまで、サポート体制を整えています。
【リフォームで賃貸のミスマッチを解消】山形県遊佐町

山形県遊佐町の空き家バンクでは、登録している賃貸物件を町が10年間借上げ、予算内でリフォームを行なってから移住者に貸し出すという方法をとっています。
空き家物件では修繕が必要になることが多いため、借り手と貸し手の間で物件の状態をめぐるミスマッチもしばしば起こります。自治体側がリフォームを行うことでこうした状態が解消され、12棟中11棟の入居につなげました。
移住後も、集落支援員によるフォロー体制を整え、希望者の移住を促進しています。
【多彩な登録物件で文化資源を活用】広島県尾道市

広島県尾道市では、NPO「尾道空き家再生プロジェクト」が市から委託を受けて空き家バンクの運営に携わっています。
移住・定住の促進や支援に加え、古い街並みの再生と活用による市の活性化にも取り組んでいます。尾道市の空き家バンクはここ4年間で成約実績は約70件にも上り、廃屋でも登録可能なほど要件が低いことが特徴です。
そのため、より自由度の高い物件利用が多く、カフェやギャラリー、ショップやゲストハウスなど、住居以外にも活発に利用されています。
【手頃な農地で移住者を募集】兵庫県 宍粟市

兵庫県北西部、宍粟市の空き家バンクでは農地付き空き家の契約について、1アール(10m×10m)から経営できるという条件をつけています。
これは農地法改正※でそれまでより少ない面積の農地でも経営ができるようになったためで、家庭菜園くらいの気軽な農業をしたいという利用者と、遊休農地を活用したいという自治体のニーズが合致したケースです。
こうした農地付き空き家9件を含め、宍粟市の空き家バンクは2020年度に成約数を大きく伸ばしています。
【移住者による手厚いフォロー】長野県佐久市
2008年から空き家バンクを始め、累計で400件以上の成約を果たしている長野県佐久市。
移住先として人気の立地もさることながら、空き家バンク自体も、物件の検索画面や利用方法の流れなどが地図やイラストを駆使した、とても使い勝手の良いものになっています。
また先に市内に移住した住民を相談員に起用して、地元での生活や仕事などのフォローを行うなど、多くの移住者を受け入れてきたノウハウの蓄積が活かされています。
【地域ぐるみの空き家対策】山口県周南市
空き家対策でユニークな取り組みを行っているのが山口県周南市です。この自治体では、「里の案内人」という地域住民のボランティアが空き家活用を呼びかけ、移住希望者への情報提供を行っています。
また「里の案内人」は、移住者へ地域の魅力を伝えたり、生活面の相談を受けるなど、移住者と地域との橋渡しの役割も果たしています。
空き家バンクに関するよくある質問
ここでは、空き家バンクに関するよくある質問に回答します。
空き家バンクを利用して購入する時に購入条件はある?
空き家バンクで物件を購入する際には、自治体ごとに定められた条件を満たす必要があります。たとえば、「購入後○年以上定住すること」や「地域活動に参加する意思があること」など、地域への定着や貢献を前提とした条件が設定されているケースが多いです。
ほかにも、移住者限定・若者限定・子育て世帯優遇など、自治体の人口政策やまちづくり方針に基づいた条件が課されることもあります。また、物件によっては老朽化が進んでおり、購入と同時に修繕やリフォームが義務付けられている場合もあります。
条件を満たしていないと購入できないこともあるため、気になる物件がある場合は早めに自治体の空き家バンク担当窓口に確認することが大切です。
空き家バンクで失敗例はある?怖いけど使っても大丈夫?
空き家バンクは自治体が運営しているため安心感はありますが、利用者の中には「想像と違った」「思わぬ出費がかさんだ」といった失敗例もあります。
特に多いのは、物件の状態をよく確認せずに契約し、購入後に予想以上の修繕費が発生したケースや、地域との相性が合わず早期に転出してしまうケースです。
また、自治体によっては情報更新が遅かったり、サポートが十分でない場合もあります。とはいえ、事前に内見を行い、必要に応じて建物診断士や行政書士のサポートを受けることで、こうしたリスクは大きく軽減できます。「怖い」と感じるのは当然ですが、正しい手順と確認を怠らなければ、安心して利用できる制度です。
空き家バンクを利用すれば無料で家が手に入る?
空き家バンクでは、「無料譲渡」と記載された物件が掲載されていることもあります。これは、所有者が維持管理や税金負担を手放したいため、無償で譲り渡すケースです。
ただし「家そのものは無料」でも、登記費用・契約書作成費用・リフォーム費用など、諸経費がかかる点には注意が必要です。また、老朽化が激しく、最低限の修繕が前提となることも多いため、「実質的に無料ではない」と感じる人もいるかもしれません。
自治体によってはリフォーム費用の補助金が用意されていることもあるため、上手に制度を活用すれば費用を抑えることも可能です。無料の物件に飛びつく前に、必要な経費や修繕内容をしっかり確認することが成功のカギです。
空き家バンクはSDGsの目標達成にも貢献する
このように全国各地で広がる空き家バンクの取り組みは、現在の私たちの課題であるSDGsの目標を達成するために大きな役割を果たすことにもつながります。それは一体どういうことなのでしょうか。
SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の頭文字をとった言葉で、国連で採択された2030年までに世界が達成すべき「持続可能な達成目標」の総称です。
SDGsでは解決をめざす17の目標と、それらをさらに具体的に示した169のターゲットからなります。
SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

空き家バンクが最も貢献するSDGsの目標はSDGs11番目の「住み続けられるまちづくりを」です。
これは「包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」と定義づけられており、人口減少に歯止めをかけて町を活性化させようとする空き家バンクの取り組みは、ターゲット11.3の理念とも一致します。
2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する
SDGs目標12「つくる責任 つかう責任」

家を建て、末長く人が住み続けることはそのままSDGsの目標12「つくる責任つかう責任」を体現していると言えます。
一度はその役目を失った家を空き家バンクによって再利用することは、ゴミや廃材を減らすだけでなく、新たに家を建て直す資材やエネルギーを節約し、資源の有効活用にもつながります。
このSDGs目標12が空き家バンクと関連してくるのは、以下のターゲットになります。
【12.5】2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する
【12.7】国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する
【12.8】2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする
【12.b】雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する
SDGs目標17「パートナーシップで目標達成しよう」

空き家バンクがもう一つ関連するSDGsの目標に、SDGs17パートナーシップの重要性が挙げられます。
空き家対策や地域活性化は、自治体だけの力で成功させることは困難です。不動産や民間企業、NPOなどさまざまな組織や人材が持つ知識やノウハウを活かし、地域の文化や特性に合った空き家対策を計画し、実行することが重要です。
例えば東京都調布市では、「NPO法人ちょうふこどもネット」との連携で、空き家対策に関するアイデアマラソンを企画するなど、多角的な方法で空き家対策を行っています。
「空き家」だけではない多様なパートナーシップ
空き家バンクそれ自体は、あくまで空き物件の情報提供サービスです。
しかし、ただ情報を集めて載せるだけでは、何の成果にもつながりません。空き家バンクが、本当に有益で持続可能なものであるためには、運営する側、利用する側の両方に多様なパートナーシップが必要になります。
空き家バンクの運営側
- 不動産会社やNPO、地域協力員などと連携して積極的に物件を調査
- 物件紹介の他、生活や就労支援、地元への受け入れなど、移住後のこまめなサポート体制
- 地域の魅力を積極的にアピール
移住希望の利用者側
- 物件の状態や契約条件、所有者側の事情や希望を理解
- 自治体との緊密な連携で移住後の生活や制度について確認
- 地域社会の一員として地元の人々と良好な関係を構築
まとめ
人口減少の続く日本で、空き家は今後も増え続けることが見込まれます。空き家バンクは、使われなくなった住居を有効活用することで、住宅問題や地方の過疎化の解決になるだけでなく、SDGsが掲げる目標にも大きく寄与します。
地方での暮らしに興味がある方、豊かな環境で暮らしたいと思う方は、空き家バンクを利用してみてはいかがでしょうか!
〈参考文献〉
「アフターコロナの都会と住まい、コロナ禍がもたらすまちづくりの変化とは」米山秀隆/株式会社プログレス
「地域の未来を変える空き家活用」いんしゅう鹿野まちづくり協議会編/ナカニシヤ出版
成29年度空き家バンクに関する調査 調査研究報告書
Ⅱ-4-① 自治体の空き家バンク取組事例集 空き家所有者等
「空き家バンク」の虎の巻〜メリット・デメリットと成功例
空き家バンクの制度の概要やメリット・デメリットを解説
Ⅲ.空き家の活用編
第3部 空き家対策の具体的な方向性
移住・定住事例集 – しあわせな移住 – 総務省
「地方公共団体による空き家対策支援制度」検索サイト (sumaimachi-center-rengoukai.or.jp)
空き家問題再考
歴史的資源を活用した観光まちづくり 成功事例集 – 内閣官房
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
「全国版空き家・空き地バンク」について|国土交通省
「2018年、2023年、2028年および2033年における日本の総住宅数・空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)の予測」
コロナ下で注目される“地方移住”や“二拠点生活”を「空き家」で実現 業界初の空き家プラットフォーム「FANTAS repro」提供開始|FANTAS technology株式会社のプレスリリース (prtimes.jp)
この記事を書いた人
shishido ライター
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。
自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。